これからの
幸せなはたらき方
を探求する
はたらく人の
幸福学プロジェクト
パーソル総合研究所 ×テクノロジーの進化や人生100年時代を見据え、就業者のライフスタイルやはたらき方は多様化しています。また、SDGsなど企業には自社の利益追求だけではなく、社会や従業員一人ひとりのwell-being(より良い状態)を実現する経営姿勢が強く求められています。これら不可逆的な変化の先にある、これからの「はたらき方」とはどのようなものなのでしょうか。また、組織は多様な個人とどのように向き合っていく必要があるでしょうか。これからの幸せな「はたらき方」の探求とは、はたらく一人ひとりと組織との「新たな関係」の探求でもあると考えています。
そこで、パーソル総合研究所は、「幸福学(幸福経営学)」を提唱されている慶應義塾大学の前野隆司教授と共同研究を実施しました。その成果についてご紹介します。
公開日:2020/07/15 最終更新日:2023/10/04
はたらく人の幸福学 プロジェクトについて
本研究プロジェクトは2つのフェーズに分けて実施しました。まず「フェーズ1」として、国内の就業者(20代~60代)に対して質的調査と大規模なアンケート調査を実施し、「はたらく人の幸せ」に着目した新たな経営指標(尺度)を開発。さらに「フェーズ2」として、フェーズ1の研究で見えてきた「はたらく人の幸せ」のパフォーマンスや経営への効果等について因果関係を実証しました。
研究背景・コンセプト
「はたらく人の幸せ」については、医学や公衆衛生学、脳科学や応用心理学といった学術分野を横断して関心が高まっており、国際的にもWell-being study(幸福学)における重要なテーマとなっています。このような背景から、本研究を意義あるものとするため、以下をプロジェクトの方針としています。
01
就業者側と雇用者側それぞれの価値を最大化し、統合を試みる概念として「はたらく人の幸せ」に着目し、計測手法を開発する。また、組織における効用を明らかにし、「はたらく人の幸せ」を高めるための実践的な打ち手を提示する。
02
「はたらく人の幸せ」について、先人の経験に基づいた議論だけに偏らず、先行する学際的な知見を援用し、定性調査・大規模なアンケート調査、実証研究などを通じて多角的に分析を行う。
03
本研究では、幸福感(得点)が高い人が「幸せ」で、低い人が「不幸せ」という解釈にとどまらず、「幸せ」と「不幸せ」をそれぞれ独立した概念として、2軸により「はたらく人の心の状態」を捉えることとする。
調査結果サマリ
フェーズ1
はたらく人の幸せ に関する大規模 調査・尺度開発
フェーズ2
はたらく人の幸せ に関する実証研究
フェーズ1 フェーズ2
はたらく人の幸せに関する 大規模調査・尺度開発 実証研究
はたらく上で「幸せ/不幸せ」を感じる要因と、 パフォーマンスへの影響を探る 実際の現場で「『はたらく幸せ実感』は パフォーマンスを高める」といえるのか?
フェーズ1の大規模調査では、はたらくことを通じて、人が「幸せ/不幸せ」を感じる要因を導出。また、はたらくことを通じて幸せを感じることが、個人や所属組織のパフォーマンス、ひいては企業業績を高めるということが示唆されました。
フェーズ2では、6社の企業の協力の下、従業員の皆さんに2回にわたる縦断調査※を実施しました。フェーズ1で示唆された「はたらく幸せ実感は、個人・組織のパフォーマンス、企業業績を高める」という結果について、そのような因果関係がはたらく現場でも成り立つのかを検証。また、「はたらくことを通じた幸せ/不幸せ実感」の部署/チーム内における波及効果や、多くの企業で指標として使用されている「ワーク・エンゲイジメント」や「組織コミットメント」との違いについても検証を行いました。その結果、次の3点が検証できました。
※縦断調査:いくつかの社会的因子の間の因果関係を調べるために、同一の調査対象者に対して一定の間隔をおいて同じ質問を繰り返し行う調査。
調査結果サマリ INDEX
-
はたらく上で、人はどのようなこと に「幸せ」や「不幸せ」を感じるのか?
-
人は、はたらくことを通じてどの程 度、幸せ/不幸せを感じているか?
-
従業員のはたらく幸せ実感は、組織 にとってどのような効果があるのか?
-
どのような組織マネジメントがはた らく人を幸せ/不幸せにするのか?
-
「はたらくことを通じた幸せ」は、パ フォーマンスやメンタルヘルスを高める
-
「はたらく幸せ/不幸せ」は、部署/ チーム内において波及効果がある
-
「はたらく幸せ実感」は、「ワーク・エンゲイジメント」「組織コミットメント」 を高める先行要因である 「はたらく幸せ実感」は、「ワーク・ エンゲイジメント」「組織コミットメ ント」を高める先行要因である
はたらく上で、人はどのような ことに
ことに
「幸せ」や「不幸せ」を
感じるのか?
本研究では、はたらく場面における幸せと不幸せをそれぞれ独立した概念と仮定し、「はたらく人の幸せ因子(7因子)」「はたらく人の不幸せ因子(7因子)」を同定。これらを計測する診断ツール(※)を開発しました。開発した診断ツールは、「はたらくことを通じた幸せ/不幸せの実感」を高い確度で予測できるものであり、個人や組織にとって望ましい状態(well-being)を追求する際に重要な介入の観点になると考えます。
※診断ツールには、「はたらく人の幸せ/不幸せ」各因子3項目で回答する「短縮版」と、各因子1項目で回答する「スーパーショート版」があります。状況に応じて適したものをご活用ください。
はたらく人の幸せの7因子
はたらく人の不幸せの7因子
「はたらく人の幸せ因子」 「はたらく人の不幸せ因子」 の詳細と
の詳細と 診断ツール(尺度)については、 添付資料を参照ください。
添付資料を参照ください。
はたらく幸せ/
はたらく不幸せをもたらす
7つの因子の詳細
7つの因子の詳細
人は、はたらくことを 通じて
通じて
どの程度、
幸せ/不幸せを感じているか?
では、はたらく人(国内の就業者)は、はたらくことを通じてどの程度、幸せ/不幸せを感じているのでしょうか。下図は、「私は、はたらくことを通じて、幸せ/不幸せを感じている」という設問の回答結果です。44.0%の人がはたらく幸せを、20.2%の人がはたらく不幸せを感じています。(2020年2月調査時点)
はたらく幸せ実感
はたらく不幸せ実感
では、はたらくことを通じて
幸せ/不幸せを感じている人には
どのような特徴があるのでしょうか?
「はたらくことを通じて
幸せを感じることは大事だ」
と思っている人
は、
はたらくことを通じて幸せを感じている
幸せ重視度と、 はたらく幸せ/不幸せ実感の関係
数値は相関係数
「はたらくことを通じて幸せを感じることは大事だ」と考えている人ほど、はたらく幸せを実感できている人が多いことが確認されました。はたらくことを通じて自らの仕事の中に幸せを見出そうとする前向きな姿勢は、はたらく幸せを実感するための重要なマインドセットだといえるでしょう。
※「はたらく幸せ/不幸せ実感」の数値は、はたらく幸せ/不幸せ実感の 各5設問(1~7Pt)の平均得点(以下同様)
「自由業(フリーランス)」
「自営業」の人
は、
はたらく幸せ実感が高く、
「正社員」の人
は低い傾向
雇用形態別にみた、 はたらく幸せ/不幸せ実感
はたらく幸せ実感TOP3
自由業
フリーランス
自営業
専門家
医師・弁護士・
会計士等
はたらく不幸せ実感TOP3
正社員
公務員・
団体職員
契約・
派遣社員
雇用形態別に、はたらく幸せ実感とはたらく不幸せ実感について集計を行ったところ、最もはたらく幸せ実感が高かったのは「自由業(フリーランス)」であり、次いで「自営業」、医師や士業の「専門家」となりました。一方、企業に勤める「正社員」は、はたらく幸せ実感が全体平均よりも低く、はたらく不幸せ実感が最も高い傾向が見られました。

前野教授
「社長になりたい」と思わない人は社長になれないように、「幸せにはたらきたい」と思わない人は幸せにははたらいていないという興味深い結果が得られました。幸福学研究者として、声を大にしてお伝えしたいです。幸せな人は、創造性が高く、生産性が高く、欠勤率が低く、離職率が低く、健康で長寿だということが研究結果として知られています。つまり、幸せにはたらくべきなのです。職種により幸せ実感の平均値が異なりますが、そんなことはまったく気にしなくてよいのです。あなた自身が「幸せにはたらく」と決意することが、幸せで豊かなワーク&ライフにつながります。幸せにはたらきましょう。
従業員のはたらく幸せ実感は、
組織にとってどのような
効果があるのか?
従業員がはたらくことを通じて幸せを感じることは、経営にとって福利厚生や健康促進の観点以外にどのような効果が期待できるのでしょうか。はたらく人の幸せ/不幸せ実感とパフォーマンス等との関係を確認しました。
はたらく幸せ実感が
高い人ほど、
高い人ほど、
個人・組織の
パフォーマンスが高い
パフォーマンスが高い
パフォーマンスへの影響
(偏差値 ※)
(偏差値 ※)
はたらく幸せを実感している従業員ほど、個人のパフォーマンスが高く、所属組織のパフォーマンスも高い傾向が確認されました。反対に、はたらく不幸せを実感している従業員ほど、個人パフォーマンス、組織パフォーマンスともに低下しています。
※数値は、調査対象者平均を50とした偏差値
はたらく幸せ実感は、
個人・組織のパフォーマンスを高め、
企業業績に影響を与える(仮説検証)
「はたらく幸せ実感が、個人パフォーマンス、組織パフォーマンス、さらには企業業績にもプラスの影響を与える」との因果モデルを検証したところ、適合度の高い有意なモデルであることが分かりました。従業員が幸せにはたらいていることは、個人の域を超え、組織や企業業績にまで影響することが示唆されたのです。
はたらく幸せ実感が高いほど
継続就業意向は高まり、
転職意向は低下
継続就業意向/転職意向への影響
従業員のリテンション課題として、継続就業意向や転職意向と、はたらく幸せ実感の関係を確認しました。結果、はたらく幸せを感じている人ほど、自組織において継続してはたらきたいとの意向が強く、転職意向は低いことが確認されました。従業員のリテンションを考える際、従業員がはたらく幸せを感じられているかどうかに着目することは肝要であるといえるでしょう。
はたらく幸せ実感が高いほど、
「はたらき続けたい年齢」
が上昇し、
イヤイヤはたらく期間が短い
はたらき続けたい年齢/ はたらき続けなくてはいけない年齢への影響
今後、人がはたらき続ける期間はより長くなると想定されます。そこで、「その年齢までは、はたらき続けなければいけない」と考える年齢と、自発的に「この年齢まで、はたらきたい」と思う年齢とのギャップを確認しました。結果、はたらく幸せを感じている人ほど「イヤイヤはたらく期間(非自発的就業期間)」が短いことが確認されました。

前野教授
分析では、幸せな社員は個人のパフォーマンスが高く、それが組織のパフォーマンスや売上につながっていく傾向を示すことができました。ただし、人は企業のためにはたらくのではありません。一度限りの人生で、悔いなく社会に貢献し、充実するためにはたらくのです。仕事を通じて幸せを感じ、自らのやりがいのために長くはたらきたいと思う幸せな人がさらに増えていくことを切に願います。
どのような組織マネジメントが
はたらく人を幸せ/不幸せ
にするのか?
組織は、従業員のはたらく幸せ実感を高めるために、どのような取り組みができるのでしょうか。はたらく幸せ/不幸せ実感に影響を与えるマネジメント要因について、組織マネジメント、上司の職場マネジメントの2つの観点から分析しました。
組織目標の落とし込みや
ワークライフバランス、
育成の手厚さ
は、
はたらく幸せ実感を高める
はたらく幸せ実感に影響を与える人事施策
はたらく幸せ実感を高めるには、個人目標と組織目標を紐づけるために、目標設定時に上司とよく話し合う場を設けていたり、昇進・昇格の基準がオープンであったりするなどの要因が最も影響していました。次いで、ワークライフバランスのとりやすさや育成の手厚さがプラスの影響を与えていました。一方、異動・転勤の多さや定年までの雇用を前提とした退職金制度等の終身雇用システムは、今日の就業者にとってのはたらく幸せ実感にはマイナスの影響を与えることが示唆されました。
異動・転勤の多さ、新卒偏重
は
はたらく不幸せ実感を高める
はたらく不幸せ実感に影響を与える人事施策
はたらく不幸せ実感を高めてしまう要因としては、異動・転勤の多さや、幹部層などに新卒入社者が多いといった新卒偏重が挙げられます。一方、はたらく幸せ実感を高める要因として確認された組織目標の落とし込みやワークライフバランス、育成の手厚さなどについては、はたらく不幸せ実感を低減させる効果が見られました。
「目標の設定」「適切な評価」
「ねぎらいの言葉をかける」
行動
は、
行動
は、
はたらく幸せ実感との関連が強いが、
実施率が低い
はたらく幸せ実感と関連の強い ポジティブな上司マネジメント
「一緒に個人的な仕事の目標を設定」「仕事ぶりに見合った評価」「日常的に感謝やねぎらいの言葉をかける」といったマネジメント行動は、部下のはたらく幸せ実感との関連が強いものの、職場での実施率が30%未満と低いことが分かりました。あたりまえのようにも思えますが、改めて振り返るべき行動といえるでしょう。
「自分が一番正しいと思っている」
「自分を客観視できて いない」
いない」 「数値や結果だけを求める」行動
は、
はたらく不幸せ実感との関連が強く、
実施率がやや高い
はたらく不幸せ実感と関連の強い ネガティブな上司マネジメント
「自分が一番正しいと思っている」「自分を客観視できていない」「数値や結果だけを求める」といったマネジメント行動は、部下のはたらく不幸せ実感との関連が強く、かつ実施率が20%以上と比較的高い傾向にありました。マネジャー自身ではなかなか気づけず、つい取ってしまっている行動かもしれません。自分を客観視するメタ認知能力は、部下を不幸せにさせないためにもマネジャーとして必要不可欠な能力要件といえるでしょう。
「はたらくことを通じた幸せ」は、
パフォーマンスやメンタルヘルス
を高める
「『はたらくことを通じた幸せ』が
個人・組織パフォーマンスを高める」
という
因果関係は、
はたらく現場でも実証
「はたらくことを通じた幸せ(因子の状態および実感)※」は、組織・仕事に対するポジティブな行動を促すとともに、個人・組織のパフォーマンスを高めるという因果関係が明らかになりました。従業員のはたらくことを通じた幸福を追求することが、福利厚生としての意味合いだけでなく、パフォーマンスの向上といった経営上の利益をももたらすことが定量的に確認できました。
※「因子の状態および実感」は、「はたらく幸せ/不幸せ実感」の度合い、および「はたらく幸せ/不幸せの各7因子」の状態を指す。以降同様。なお、「はたらく幸せ/不幸せの各7因子」の詳細は こちら
「はたらく幸せ実感」や
「はたらく幸せ因子の状態」が
パフォーマンスに与える影響
「はたらくことを通じた幸せ」は、
メンタルヘルス
にも良い影響あり
「はたらく幸せ(因子の状態および実感)」には、心理的ストレス反応や睡眠の質を良好にする効果があったのに対し、「はたらく不幸せ(因子の状態および実感)」にはこれらに対する悪影響が見られました。
「はたらく幸せ/不幸せ」の実感度合いや各7因子が、 メンタルヘルスに与える影響 「はたらく幸せ/不幸せ」の実感度合い や各7因子が、メンタルヘルスに 与える影響
はたらく幸せ実感は、
「幸せにはたらくべき」という
価値観を強める
「はたらく幸せ実感」が高まると、幸せにはたらくことを重視するようになり、「はたらく不幸せ実感」が高まると、不幸せを回避することを重視しなくなる(裏を返せば、不幸せを許容していってしまう)という因果関係が明らかになりました。つまり、「はたらく幸せ/不幸せ実感」は従業員がもともと持っている価値観によってコントロールできるというよりも、置かれた境遇の「幸せ/不幸せ度」に応じて価値観が変化することが確認されました。
「はたらく幸せ実感」「はたらく不幸せ実感」が 価値観に与える影響
「はたらく幸せ/不幸せ」は、
部署/チーム内において
波及効果がある
部署・チームの「幸せ実感」が
高いと、
高いと、
そこではたらく
個人の
幸せ実感」も高まる
幸福学の先行研究では、幸福が人から人へと伝染することが示されていますが、所属部署・チーム内でも同様の効果が確認できました。具体的には、「はたらく幸せ実感」「はたらく不幸せ実感」が、所属組織内の周囲と個人の間で相互に影響し合う波及効果が確認できました。
「はたらく幸せ/不幸せ実感」の 組織における波及効果
「はたらく幸せ実感」は、
「ワーク・エンゲイジメント」
「組織コミットメント」を高める
先行要因
である
パフォ―マンスや行動を促進する
効果は、
効果は、
「ワーク・エンゲイジメント」
「組織コミットメント」よりも
「はたらく幸せ実感」のほうが強い
「はたらく幸せ実感」は、「ワーク・エンゲイジメント(仕事に対するポジティブで充実した心理状態)」や「組織コミットメント(組織への愛着や帰属意識)」を高める先行要因となっており、両者を媒介してパフォーマンスやポジティブな行動を促進しているという因果関係が分析から確認できました。また、その影響の強さは、3指標の中でも最も強いことも分かりました。既存概念である「ワーク・エンゲイジメント」や「組織コミットメント」を高めるためにも、幸せ実感を改善していくことが必要です。
「はたらく幸せ実感」は、「ワーク・エンゲイジメント」や「組織コミットメント」 を媒介して、パフォーマンスやポジティブな行動を促進する 「はたらく幸せ実感」は、 「ワーク・エンゲイジメント」や 「組織コミットメント」を 媒介して、パフォーマンスやポジティブな 行動を促進する
3つの概念のパフォーマンス/行動
に対する促進効果の違い
~パフォーマンス、行動に対する
直接的な効果の大きさを比較~
フェーズ2の実証研究の結果、はたらくことを通じて幸せを感じると、ワーク・エンゲイジメントや組織コミットメントが高まり、組織・仕事に対するポジティブな行動が増えるとともに個人・組織のパフォーマンスが高まるという因果関係が明らかになりました。また、幸せにはたらけていると、「幸せにはたらくことは重要」という価値観に変化することや、はたらくことを通じた幸せ/不幸せがチーム内で波及することも示されました。
本研究プロジェクトの結果、はたらくことを通じた幸せは、企業と従業員の双方に利益をもたらすことが実証されました。時代の潮流として、社会や従業員のwell-beingを実現する経営姿勢が求められる中、はたらくことを通じた幸せ/不幸せ、並びにその14因子は、企業と多様な従業員が共に目指すことのできる非財務指標(人的資本に関するKPI)のひとつとして有効といえるでしょう。


1984年東京工業大学卒業、1986年同大学修士課程修了。キヤノン株式会社、カリフォルニア大学バークレー校訪問研究員、ハーバード大学訪問教授等を経て現在慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科教授。慶應義塾大学ウェルビーイングリサーチセンター長兼務。博士(工学)。著書に、『幸せな職場の経営学』(2019年)、『幸福学×経営学』(2018年)、『幸せのメカニズム』(2014年)、『脳はなぜ「心」を作ったのか』(筑摩書房,2004年)など多数。専門は、システムデザイン・マネジメント学、幸福学、イノベーション教育など。
本プロジェクトに寄せて
(共同研究者の前野教授より)
幸福学研究者として、これまでに「幸せの因子分析」を行ったことはありましたが、今回は、はたらくことに特化して、しかも幸せと不幸せを単なる対向概念と捉えるのではなく、はたらく幸せ/不幸せのための7×2の因子を求めることができました。これは、パーソル総合研究所と共同研究をしたからこその成果です。詳細な分析からさまざまなことが分かり、満足しています。
今後は、多くの企業・事業体で、幸せな職場づくりのための現状可視化ツールとして利用していただければと願っています。医療と健康診断の進歩により、現代人は人類史上最高に健康・長寿です。同様に、幸福度診断の進歩により、現代人にとっては、人類史上最高に幸せにはたらくことのできる時代が目前に迫っているのです。みなさん、はたらいて、笑って、人類史上最高に幸せになってください。
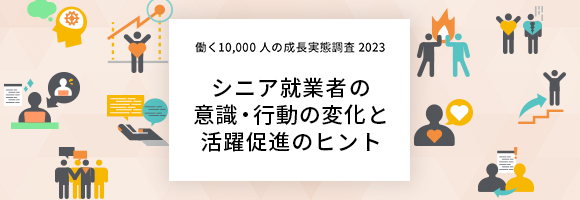


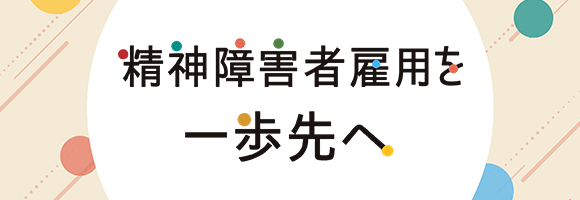
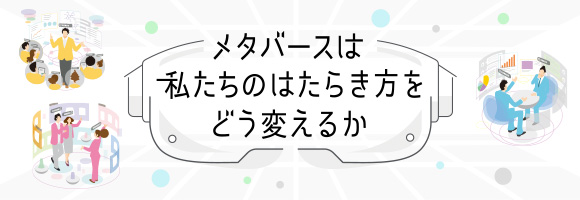
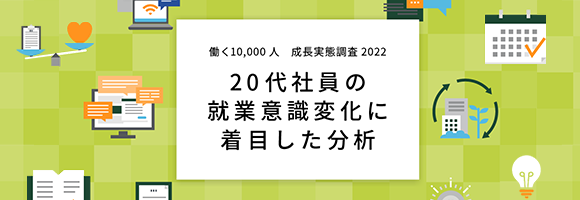
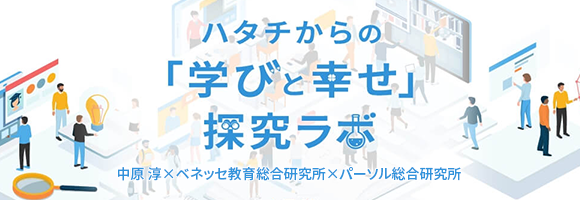


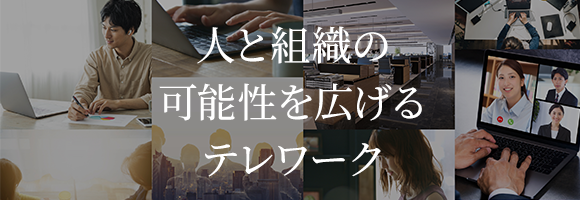
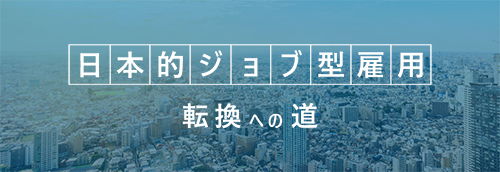


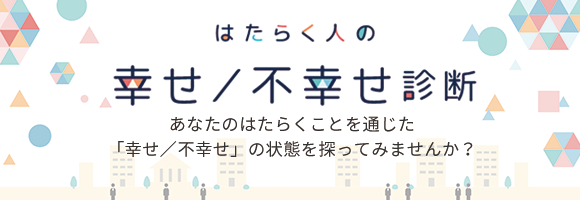
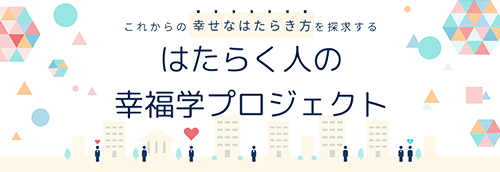

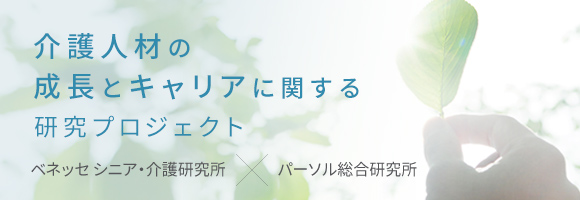
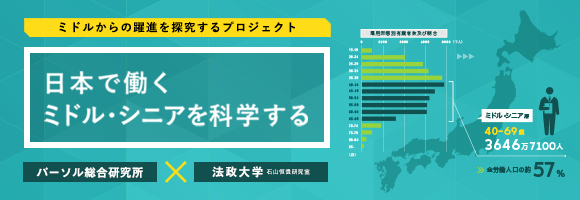

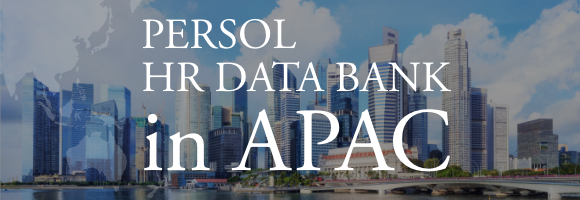
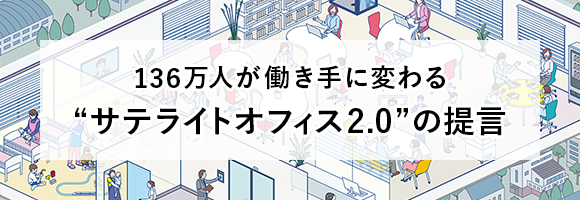

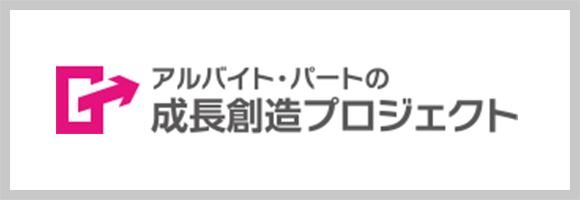
前野教授
かつてトルストイは『アンナ・カレーニナ』の冒頭で、『幸せな家庭は似ているが、不幸せな家庭にはそれぞれの不幸がある』と述べ、幸せと不幸せは対向概念ではないことを示唆しました。『職場も同様なのではないか。幸せな職場の条件と不幸せな職場の条件は単に表裏なのではなく、別々のものとして存在しているのではないか』。このような仮説の下で行ったのが本調査です。結果はご覧の通り。幸せでないことが不幸せなのではなく、幸せの条件を満たし、かつ不幸せの条件を満たさない職場が幸せな職場だったのです。はたらき方のために極めて重要な新発見と自負しています。