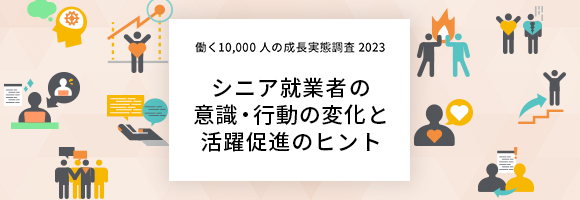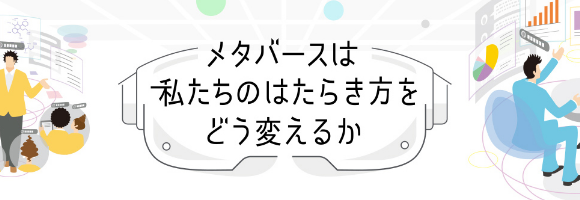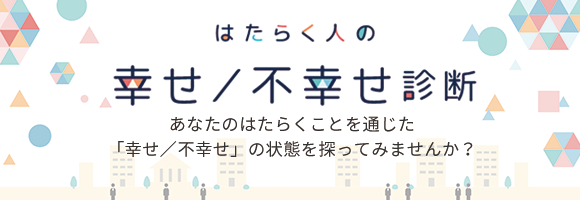アクション志向型の従業員意識調査に向けて
公開日 2009/05/01
執筆者: 総合営業本部 執行役員 元木 幹雄
従業員意識調査の課題
昨今、暗いニュースばかりが目につく。新聞の見出しにも「日経平均、バブル後最安値」「大手金融機関の破綻」「非正社員に続き、正社員の削減」等、数え上げるときりがない。このような状況のもと、企業の大きな関心事の一つに「従業員の動機付け」がある。 そこで従業員のやる気を引き出し、社内を活性化するためにはどうすべきか、そのヒントを得ようと従業員意識調査(以下、調査)を実施している企業も多い。 しかし、調査そのものは無難にこなすことができても、従業員のやる気を引き出し、社内を活性化させるといった「そもそもの目的を達成できた」と実感を得ている企業は本当に少ないようだ。当たり前の話だが、調査を実施しただけでは、従業員のやる気を引き出すことも、社内を活性化させることもできない。 先日、調査を展開している複数の企業で、調査そのものがうまく展開されているかどうか、経営者や調査を展開する事務局、及び複数の従業員からヒアリングする機会を得た。そこから浮かび上がってきた実態は「経営陣や調査を展開する事務局(以下、事務局)」と「従業員」との間の認識の差や、複数の課題だ。この課題を解決することが、本当に価値ある調査、アクションに繋がる調査を実施する前提条件と考え、本稿では4つの提言をしてみたい。
提言1:目的の周知徹底
調査目的を伝えないまま、調査を実施している企業はないだろう。しかし、従業員は「想像以上に目的を理解していない」という事実を、事務局は認識しなければならない。試しに従業員の数名をつかまえて、調査の目的を聞いてみるとよくわかる。明確に回答できる従業員は少ないだろう。大企業であれば、わざわざ従業員をつかまえて聞かなくても、目的を理解しているかどうか知る方法もある。大企業では、各種アンケートや調査など、従業員に回答依頼する施策がたくさんある。従業員から「また同じような調査を実施しているよ」という声が聞こえてくるようであれば、それも従業員は目的を理解していない証拠といえる。しかし、そのことを事務局に伝えても、問題意識を持つ事務局は少ない。調査目的はきちんと社内文書等で展開されているので「問題ない」とする事務局がほとんどだ。つまり目的の周知徹底は、とにかく伝達すればよい、と認識されているのが実態のようだ。明確な目的があったとしても、それを従業員にきちんと伝えないまま、仕事に取り組ませたとしたらどうなるであろうか。従業員は与えられた仕事を黙々とこなすことはあっても、そこにやりがいを見出すことはできないだろう。調査も同様で、明確な目的を伝えなければ、やれといわれたからやるだけで、前向きな姿勢 での回答は得られない。単に面倒なことを押し付けられていると従業員は感じるはずだ。事務局は調査の実施にあたり、背景と目的を、社長から直接、従業員に語りかけてもらう場を作ることが重要だ。大企業であれば、社長から全従業員に語りかけてもらうことは難しいかもしれない。そうであるならば最低限、担当役員や部門長が、社長のメッセージを受けて、自分の言葉で自部門のメンバーに説明してもらいたい。事務局は、質問がでればそれを受け止め、必ず回答すると同時に、そのFAQを全従業員に共有するくらい、目的の周知徹底に時間をかけるべきである。
提言2:匿名性の担保と従業員との信頼関係の構築
調査は匿名で実施することをお勧めしたい。 時々「匿名でなければ意見がいえないなんて、それこそが問題だ」「匿名だと、無責任な回答になる。責任ある回答を求めるため記名式で実施する」と声高に記 名式で調査することを主張される事務局もいる。もちろん記名式で実施してもよいのだが、その場合、普段から大きな声をあげている人、社内的に立場が高い人 の意見は引き出せるかもしれないが、社内的に立場が弱い人の本音を引き出せない可能性が高いから注意が必要だ。普段から大きな声をあげている人や社内的に立場の高い人の意見は、普段から耳にしているためよくわかっている。言いたいことがあってもなかなか言いだせない人も従業員の中には多数いるはずだ。そういった従業員も含めて「全従業員の本音を引き出す」という観点で考えると調査は匿名が望ましい。以上の理由から、弊社では匿名で調査をすることを勧め、実際に多くの場合、匿名で調査しているが、従業員から「本当は誰が回答したか確認しているでしょう?」と聞かれることがある。もちろん、インターネットで調査を実施すれば、ログから調べようと思えば調べられるし、紙での実施であれば筆跡である程度わかってしまう。「男性・女性」「20代・30代・40代・50代」「一般職・管理職」「スタッフ部門・研究部門・生産部門・営業部門・サービス部門」といった具合に属性まで回答させ、クロス集計すれば、ある程度個人を特定できることは確かだ。しかし、個人を特定できたとしても、特定しないというのが匿名での調査だ。たとえ、最悪の調査結果がでたとしても、誰が低い回答をしたのか犯人探しをするようなことはしてはならない。自由回答の中で「誰々がセクハラをしている、誰々が法令を犯している」という記載があったとしても、記載者を探し、確認するようなことはあってはならない。また、名指しされた人に「こんな意見があったが心当たりはあるか」と尋ねるようなこともしてはならない。名指しされた人が 犯人探しをするかもしれないからだ。回答した個人を特定している、ということが従業員にわかった段階で、次回からの調査は協力を得られないと覚悟すべきだ。もちろん調査依頼をすれば、会社命令ということで回答するが、信頼できるデータが得られないという意味である。ある企業で調査をしたときのことだ。この企業は2年前にリストラに着手し、指名解雇をしたばかりだった。調査結果の報告会をした際、従業員から「批判的な意見を出している従業員を探しているんでしょう?」と質問されたことがある。周囲も同調している様子だ。このような質問がでるということは、調査結果はあまり信頼できない。会社を恐れてよい意見しか出されていないだろうと、容易に想像できるからだ。従業員からの信頼は、会社がどれだけ、従業員に対して誠実に接しているかで決まる。もし信頼を失っているのであれば、回復するには時間がかかる。特効薬はない。調査を匿名で実施するといったらそれを厳守する。地道に従業員からの信頼を回復するしかない。従業員も「調査結果は個人を特定し、特定の人間に不利益を被らせることはない」と認識したら本音を出すようになるだろう。
提言3:仮説検証型の設問設計
調査を初めて導入する際、事務局は「初めてなのでよくわからない。初年度は標準的な設問で実施しよう」と安易に考えることがある。そんな場合は大抵、事務局に「問題点は何か」という仮説がないために、調査をかけることで問題を発見しよう、と考えている。そうなると当然、調査における設問も網羅的に設計することになり、回答者である従業員は、いいたいこと、聞いてほしいことが回答できる設問になっていない、ということになる。調査結果のあと、設問がいまいち だった、という反応がかえってくる。初年度だから、という理由で、設問を真剣に考えようとしない企業は、2年目以降は設問を見直すかといえば、多くの場合はそうならない。「前回比較をしたいので、設問を変えると比較できない」等といった理由で初年度と同様の設問になるのだ。そうなると、従業員がいくら設問がいまいちだ、といっても変わること はない。更にこんな企業は、毎年、調査を実施しても、従業員の動機付けを目的としたアクションに取り掛かることは極めて少ない。なぜならば、調査終了後にはじめて問題を探ることになるのだが、網羅的に設問が設計されているため、得られる結果も抽象的で、問題点を特定するのが極めて難しいのだ。仮に問題点を特定できても、分析に時間をかけ、社内でオーソライズされるまで調査後、数ヶ月は平気で経ってしまうのだ。そこからアクションプランを練るため、あっという間に半年くらいは過ぎ去ってしまう。変化の激しい時代において、半年も時間をあけると、アクションに移すときには問題点が変わってしまっている、ということはよくある出来事だ。つまり「問題点は何か」。調査前に仮説を掲げ、その問題点を検証するような設問設計をして、調査を実施することが望ましい。そうなると自ずと設問は、その問題点を検証するようなものとなり、より具体的で、従業員にとって身近な設問になっているはずだ。更に、事前には問題点だけではなく、その問題点が検証さ れた暁には、「このような解決策を展開しよう」と、ここまで仮説を持っておけば、調査後、すぐにアクションにうつせる。こんな話をすると「仮説が間違っていたらどうするんだ」という意見が出てくることもある。もちろん全くの検討違いの仮説を掲げてしまっていた、ということもあり得なくはない。しかし、そのリスクがあったとしても仮説を掲げ、自社独自の設問設計することをお勧めしたい。網羅的に設問で問うても、抽象的な結果 しか得られない。結果、抽象的な結果を、更に深堀するために追加調査か、インタビューなどで問題点を明らかにしなければアクションに移せるだけの材料が得 られないからだ。そうなると上述した通り、結局は時間切れで、何もアクションできないことになる。また仮説は、仮説と検証のプロセスを繰り返すと、精度の高い仮説を掲げられるようになる。見当違いの仮説などは掲げなくなるのだ。そうなったときには、まさに自社に必要な仮説に基づいた設問設計から調査実施、問題の検証とアクションプランの実行と、スピーディーな問題解決のサイクルをまわせることになる。
提言4:調査結果のフィードバック
調査結果は、従業員に必ずフィードバックすべきだ。それもできるだけ早くフィードバックすることが求められる。
しかし、従業員にフィードバックするまで、本当に時間がかかる。通常、調査終了後に調査結果を分析し、報告書を作成する。そしてその報告書を経営者に報告してから従業員にフィードバックする。これはよいのだが、経営者に報告する機会というのが、月に1回しか実施していない経営会議の場であることも少なくな い。この場合、重要案件が山積みになっていると報告が後回しにされる。その結果、報告書が出来上がっているにも関わらず、1ヶ月以上も従業員へのフィード バックが遅れるということがよくある。調査結果は、従業員にとって関心が強いものである。従業員に対し調査への協力依頼したものなので、できるだけ早くフィードバックするのは最低限の礼儀とい える。稀なケースで、信じられないのだが、時期を逃してしまいフィードバックしなかったという企業もある。もしフィードバックをしないというのであれば、調査など実施しないほうがよい。フィードバックがなければ改善は望めないし、むしろ従業員の不満がたまるだけだからだ。
またフィードバックの方法も重要である。事務局に対して「フィードバックをしていますか?」という質問をすると、ほとんどの事務局から「もちろんフィード バックしています」という回答を得る。しかし、面白いことに、その企業の従業員に聞くと「フィードバックされていない」と回答を得ることも多いのだ。事務局がフィードバックしている、といっているにも関わらず、従業員がフィードバックされていないという企業は、たいてい調査結果の抜粋を「掲示板に載せる」 「社内報に載せる」「回覧する」といったフィードバックの方法をとっている。従業員にこの事実を伝えると「確かにあったような気がする」といい、事務局は「見ない従業員が悪い」という。しかし、調査結果をそのまま「掲示板に載せる」「社内報に載せる」「回覧する」のでは、フィードバックとはいえない。その調査結果を受け止めて「どのように会社は認識し、これからどうすべきなのか」まで、経営者や事務局が、自らの言葉で直接、従業員に伝えてはじめて、フィードバックしたといえるのではなかろうか。
むすびにかえて:アクションに結びつけるために
調査は、調査そのものが目的ではなく、従業員のやる気を引き出し、社内を活性化させることが目的である。そのために、調査結果にて問題点を検証し、アクションに繋げなければ意味がない。しかし、実際のところアクションまで繋がっている企業は極めて少ない。これは考え得るさまざまな局面から調査・分析を行い、その結果をベースに問題を整理・抽出し、アクションプランを組み立てようとしているからだと思う。これでは情報をできるだけ集め、数多くの分析を行わなくてはならないので、時間が無限にかかる。短期間で問題を発見し、解決しなければならない場合、間に合わない。頭がよい人や、伝統的な企業ほどこの傾向が強いように感じる。理屈先行 で、意思決定に時間がかかり、人の提案にはまず批判やあら探しから入る。これではスピーディーにアクションには取り掛かれない。そうではなくアクション志向型の調査を実施したい。まずは問題点やアクションプランといった結論から考えるのだ。取り組むべき施策と問題点を仮説として掲げ、調査・検証によって問題点とアクションプランを2~3程度に絞り込むのだ。そしてすぐにアクションに繋げる。それができたら次に進むのだ。同時にあれこれ考え、いろんなことに手をつけるより、ここだけは改善したいという問題に集中して、取り組んでいった方がうまくいくものである。
執筆者紹介

総合営業本部 執行役員
元木 幹雄
Mikio Motoki
人事教育コンサルティング会社及び遠隔通信制(オンライン)ビジネススクールにて営業や企画スタッフを経験後、2001年に富士ゼロックス総合教育研究所(現 パーソル総合研究所)に入社。人事制度及び人材育成制度の導入・定着に向けたコンサルティング、人事情報システムやタレントマネジメントシステムの導入支援、リサーチ&アセスメントの企画・実行支援に従事し、現在に至る。産業能率大学大学院経営情報学研究科(MBA)修了。
次のコラム
おすすめコラム
【経営者・人事部向け】

パーソル総合研究所メルマガ
雇用や労働市場、人材マネジメント、キャリアなど 日々取り組んでいる調査・研究内容のレポートに加えて、研究員やコンサルタントのコラム、役立つセミナー・研修情報などをお届けします。