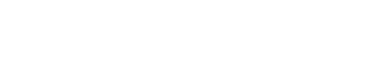PERSOL HR DATA BANK in APAC
インドネシア労働法制
インドネシアは、国際労働機関(ILO)の結社の自由、団結権、団体交渉権等の条約をアジアでもいち早く批准した国であり、労働法制は非常に労働者に有利に設計されている。解雇の際には正当事由が必要であり、労働関係裁判所の許可さえも必要とされている、解雇の際に多額の法定の退職金が発生する、最低賃金が定められているなどの点に会社は注意が必要である。
さらに、労働組合の活動や労働組合同士の連携も活発であり、ストライキも多発しており、法定の退職金以上の支払いを余儀なくされる機会も多い。
また、外国人のビザの取得にも時間がかかるなど、外国人の就労に対しても寛容ということはできないなど、会社にとって労働管理が非常に困難な法域の一つであるといえよう。
なお、2020年11月2日に施行された雇用創出に関する法律2020年11号等の一連の改正により、労働法は改正されている。労働法は2024年10月15日、MK決定168/2023により憲法裁判所において一部違憲と決定された。同法および施行規則による改正の内容、憲法裁判所の判決については適宜本文で言及した。
労働管理において気を付けなければならない点、労務慣行の特徴、近年の労働政策の状況
法規
ジャワ、スマトラをはじめ多数の島々からなるインドネシアは、その地理的な条件から元来多民族国家であり、宗教・言語等文化的背景を異にする国民を擁する。このため、法規についても共同体ごとの慣習法(Hukum Adat)が存在していたほか、イスラム教地域ではイスラム法、オランダ統治下では大陸法(シビル・ロー)と様々な影響を受けて今日に至る。インドネシアは現在も日本と同様の大陸法の法体系に属する。
インドネシアの法規は1945年インドネシア共和国憲法を頂点とし、法及び規制の形成に関する法律によりその下に、法律(Undang-Undang)、法律代行政令(Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang)、政府規則(Peraturan Pemerintah)、大統領規則(Peraturan Presiden)、その他法令(地方条例(Peraturan Daerah)等を含む)の順で、序列が定められている。しかしながら、法令間の秩序は保たれていないことがあり、一部で矛盾・抵触がある状態が確認されながら、是正されていないこともある。このため、現地法律家と協力してインドネシアの法・法制に通じていることが必要となることも少なくない。
※コモン・ロー/シビル・ローの概略
「コモン・ロー」とは、イギリスのほかかつて大英帝国領であった諸国(アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドなど)で中心に採用されている、伝統・慣習・先例に基づいて判断してきた判例を重視する法体系を指す。
他方、「シビル・ロー」とは、フランス・ドイツなどの大陸側で発達した概念であり、コモン・ローに比べて制定法を重視する法体系である。なお、日本は、シビル・ローの法体系に属する。
豊富な労働力と労働者有利の労働法制
世界第4位の人口(2億8千万人超)を誇り、かつ労働力人口がその約半数を超えるインドネシアの潜在的な労働力はその人口構成から長らく注目されている。人口及び労働力人口はなおも上昇しており、活発な内需と共に経済もここ5年間、GDP5%前後を保ったまま推移している。
このように労働力の規模は増大していると予想されるインドネシアであるが、労働法の観点からいえば、労働者に対し手厚い保護を行っている国であるため、インドネシアに進出する会社にとって事業を展開していく上で配慮が必要となることが多い。例えば解雇は、解雇原因が法律で規定されており、産業関係紛争解決機関(産業関係裁判所)の許可を得なければならないし、懲戒解雇の場合であったとしても退職金の支払いが義務付けられる場合もある。更に、インドネシアには権利意識の強い労働者が多く、労働組合も労働者の権利を守るために積極的な役割を果たしている。このため工業団地等地域によっては、ストライキやデモ等の労働組合対策を講じることが勧められる。一定以上の労働者を有する会社には、労働組合のほかに、二者協力機関という会社・労働者双方で構成される意見交換機関を設置し、各所で労働者の意見が反映しやすくなるよう配慮するように勧められる。
定年について、インドネシアでは直接定年を定めた法令はない。ただし、年金受給開始年齢については法令で定められており、2043年までに暫時の段階的上昇が予定されているため注意を要する。政府規則(政府規則2015年第45号)によれば、2021年時点で定年は57歳であったが、2022年には58歳になり、3年ごとに1歳分ずつ65歳になるまで(2043年に)上昇する予定である。また、労働局は各企業に対して同年金受給開始年齢と定年を同じ歳とするよう指導している点にも注意が必要である。
宗教的配慮
世界最大のイスラム教国であるインドネシアでは、祈祷への配慮が法で義務付けられており、労働者は自身の宗教的価値につき尊重される権利を有する(労働に関する法律2003年第13号(以下、「労働法」)86条1項c)。会社の側では、労働者に宗教上義務付けられている祈祷、及び神の崇拝の十分な機会を与えなければならず(労働法80条)、宗教上義務付けられる宗教的行為への参加のために会社での勤務ができない場合にも賃金を支払わなければならない(労働法93条2項e)。賃金の保障のみならず、宗教上の理由から欠勤をしたことを理由とする解雇をすることも許されておらず(労働法153条1項c)、信仰や宗教の違いを理由とする解雇も認められていない(同条項i)。宗教的配慮に関するインドネシアの特色として、マレーシアやシンガポールにはない宗教祭日手当(後述「4-5賞与・宗教祭日手当等」)の労働者への支払いが義務付けられている。
インドネシア語の使用
インドネシアでは、インドネシアの法人や政府当局、国民との間で契約を締結する場合に、インドネシア語による記載が義務付けられている1。
労働協約、有期個別雇用契約及び就業規則でも、インドネシア語による作成が法令上又は実務上義務付けられる(労働法57条1項、116条3項、同条4項)。これはインドネシア行政の便宜のほか、特に労働者保護の観点から、労働者において十分に自己の契約の内容が理解できるようにとの配慮によるものとされている。もし労働契約がインドネシア語以外も併せて作成された場合で、両言語間で解釈の疑義が生じた場合には、インドネシア語版が優先する旨が法定されており(労働法57条2項、116条3項、同条4項)、官公庁へのインドネシア語での書面提出が求められる実務上の要請と併せて、インドネシア語での書面の作成が主となる。
基本的な労働法制の概要
基本的労働法制
労働法及び民法(第3編第7A章)において雇用契約(又は労働契約)に関する規定が設けられている。労働法については以下で述べるが、民法では、労働契約は、一方当事者である労働者が報酬の見返りとして一定期間、他方当事者である会社に対して労働を提供する契約として定められている(民法1601条a)。民法ではこのほかに雇用契約の総則、会社側・労働者側の義務、契約の終了方法等が規定されている。労働に関しては労働省(Ministry of Manpower)の所管となっており、労働法による定めのほか、政令等による補充・拡充がある。
労働法
労働法が、労働に関係する最低限の基準及び条件等を定めた法律であり、インドネシアにおける最も基本的な労働法規である。
-
近年の労働法改正
労働法は、2020年施行の雇用創出に関する法律2020年第11号(別名「オムニバス法」であり、以降「オムニバス法」という)に伴う一連の改正2によって、一部の内容が変更されている。なお、本資料において「労働法」という場合は、特に説明がない限り、これらの改正を踏まえ、現状有効となっている労働法を指す3。
-
対象者
労働者は、賃金又はその他の形態の報酬のために働く全ての者と定義されている(労働法1条3項。このため、極めて幅広く労働法の対象者が設定されており、外国人労働者や役員をも含むものとされている。使用者については、個人、事業者、法人そのほかの形態により賃金を支払い、労働者を雇用する者と定義されている(同条4項。駐在員事務所も含まれる(同5項c))。
雇用契約
雇用契約は、労働者と会社の間での合意で、両者の労働の条件、権利並びに義務について規定するものとされている(労働法1条14項)。雇用契約は労働協約に違反してはならず(労働法127条1項)、雇用契約において労働協約よりも労働者にとって不利な条件が定められている場合には、雇用契約の該当範囲について無効となる(同2項)。
会社が労働者を直接雇用する場合、次の3つ、①期間の定めのないもの、②期間を定めたもの(有期契約)又は③日雇労働のいずれかによることになる。
雇用契約書は法的に拘束力のある書面を二部作成し、会社と労働者がそれぞれ一部を保管する(労働法54条3項)。撤回及び変更には両者の合意が必要である(労働法55条)。
- 雇用契約書における必須記載事項(労働法54条1項)
-
a.会社の名称、所在地及び業種
b.労働者の氏名、性別、年齢及び住所
c.職業又は職種
d.勤務地
e.賃金及び支払方法
f.会社及び労働者の権利及び義務を記載した職務要件
g.雇用契約の効力発生日及び有効期間
h.雇用契約書が作成された場所及び日付
i.雇用契約当事者の署名
(e及びfについては、会社の内規、労働協約、法令等に違反してはならない(同2項))
下記でみる有期雇用契約による場合は、必ず書面により、インドネシア語で雇用契約書を作成しなければならない(労働法57条1項)。インドネシア語に加えて、外国語で雇用契約書を作成する場合には、言語間で文章の解釈に齟齬が生じたときにはインドネシア語版が優先されるため注意が必要である(同2項)。
雇用契約を締結した労働者に対し保障される主な待遇は以下の通りである。
主な直接雇用による労働者の分類については以下の通りとなる。
①期間の定めのない雇用契約
期間の定めのない雇用契約について、業務は限定されない。個別雇用契約は、口頭4、又は書面のいずれによっても成立する(労働法51条1項)。また、退職金の支払いが必須になる点で特色を有する(労働法156条)。
②有期雇用契約
有期雇用契約については、下記で列挙される特定の業務についてのみ認められ(労働法59条1項、政府規則2021年35号4条、5条)、雇用契約への署名後3営業日以内に、会社は労働省にオンラインで登録しなければならない(政府規則2021年35号14条1項)。オンライン登録が利用できない場合には、署名後7営業日以内に書面で登録を行う必要がある(政府規則2021年35号14条2項)。また、労働協約や、雇用契約、就業規則で特に規定されていない限り、会社は契約報奨金を除く退職金を提供する必要はない(労働法61A条1項)。
上記の要件を満たさない特定の期間の雇用契約は、期間の定めのない雇用契約とみなされる(労働法59条3項)。
- 有期雇用契約による許される業務の分類(労働法59条1項、2項、政府規則2021年35号4条、5条)
-
(1) 期間による分類
- a.短期で終了すると推定される業務
- b.季節的な業務
- c.新製品、新事業、又は試験段階にある補助製品に関連する業務
- a.一度で完成する業務
- b.一時的な業務
上記(1)の期間による分類に基づく業務は、延長期間も含めて、最長5年間行うことができる(政府規則2021年35号8条及び労働法55条3項に関する憲法裁決定168/2023)。
有期雇用契約の一種として、日雇契約をすることも可能である。日雇契約の場合には1カ月21日未満の労働が限度とされており、これに反して3カ月連続で毎月21日以上勤務させた場合、無期限雇用とみなされる(政府規則2021年35号10条)。日雇契約は書面で作成する必要がある(政府規則2021年35号11条)。この場合にも、会社は雇用契約に署名後3営業日内に労働省にオンラインで登録しなければならない(政府規則2021年35号14条1項)。オンライン登録が利用できない場合には、署名後7営業日以内に書面で登録を行う必要がある(政府規則2021年35号14条2項)。このときの雇用契約書には、記載事項として、①会社の名称・所在地、②労働者の氏名・住所、③仕事の内容、及び④賃金・報酬の額等が定められていなければならない(政府規則2021年35号11条)。
政府規則2021年35号は契約報奨金を定めている。契約報奨金とは、有期雇用契約の終了時に、有期雇用契約の契約社員に支給する金額をいう。会社は有期雇用契約の終了時に契約報奨金を支払う必要がある(政府規則2021年35号15条2項)。契約報奨金は、少なくとも1ヶ月継続して勤務した労働者に支給される(政府規則2021年35号15条3項)。有期雇用契約が延長された場合、まず延長前の契約が終了した際に契約報奨金が支給され、延長された期間が終了した際に、延長された期間に応じて計算された契約報奨金が支払われる(政府規則2021年35号15条4項)。当該契約報奨金に関する規定は、外国人労働者には適用されない。
契約報奨金は以下の計算式で計算される(政府規則2021年35号16条1項)。
契約報奨金の支払いを計算する際の基礎となる上記の「給与」は、以下の内容となる(政府規則2021年35号16条2項、3項、4項)。
a. 基本給および固定手当
b. 当該会社の賃金構成として基本給及び固定手当という形が規定されていない場合には手当なしの給与
c. 当該会社の賃金構成が基本給と変動手当で構成されている場合には、基本給
-
試用期間
無期雇用の労働者についてのみ、会社は雇用契約において明記していれば、最長3カ月間の試用期間を設けることができる(労働法60条)。口頭での雇用契約の場合には、雇用契約にて試用期間を設ける旨を記載しておく必要があり、明記がない場合、試用期間として認められない(労働法60条解説文)。
有期雇用の労働者については前述の通り、会社は試用期間を設けることができず、これに反する規定は無効となる(労働法58条)。
-
労働時間
労働時間は週40時間以内であり、かつ一日当たりでは週5日勤務の場合に8時間、週6日勤務の場合に7時間が限度となる(労働法77条2項)。
会社は、労働者が休憩し職場を離れることを許可する義務がある。なお、4時間以上連続した労働については、30分以上の休憩を与えることが義務付けられており、当該休憩時間は労働時間に算入されない(労働法79条2項a)。
-
労働協約
労働協約とは、労働組合5と会社との間の交渉の結果締結される契約のことであり、これと相反する雇用契約で、労働者に不利に働くものについては雇用契約がその範囲で無効となる(労働法127条1項、2項)。又、雇用契約に定めのない場合についても、労働協約での規定が補充される(労働法128条)。
労働協約は一つのみ作成され、原則としてこれが全労働者に対し適用される(労働法118条)6。両者によって署名された労働協約は県・市(会社が同一県・市内に所在する場合)、州(会社が異なる県・市に所在する場合)あるいは産業関係育成総局(会社が異なる州に所在する場合)へ提出しなければならず、担当官による審査の後、作成に係る当事者が署名をし、労働省で提出及び登録を行う(労働法132条1項、同2項)。
労働協約には最低限下記の事項が含まれていなければならない(労働法124条1項)。
-
a.会社の権利義務
b.労働組合及び労働者の権利義務
c.有効期間及び効力発生日
d.労働協約作成当事者の署名
会社と労働組合は、社内の全労働者に労働協約の内容又はそれに加えられた変更を通知する義務がある(労働法126条、2項)。会社は、労働協約のテキストを印刷し、会社負担にて労働協約を各労働者のために印刷・配布しなければならない(労働法126条2項、3項)。労働協約は、開始から2年間有効であり、労働協約が有効である期間は、会社と労働組合の間の書面による合意に基づいて、1年間延長できる(労働法123条1項、2項)。
-
a.会社の権利義務
-
アウトソーシング
労働法は第64条で、自社の業務をアウトソーシングできると定め、第66条でアウトソーシング会社(Perusahaan alih daya)に関する規定を置いた。アウトソーシングについては、改正オムニバス法改正前の労働法では、可能な領域について制限が規定されていたが、改正後の現在は主要な業務に限るといった制限は規定されていないため、今後はより広くアウトソーシングが利用される可能性がある。
その他の法律
-
労働組合法等
インドネシアは、結社の自由および団結権の保護に関する条約(ILO87号条約)及び団結権及び団体交渉権に関する条約(ILO98号条約)批准国であり、労使関係に関する関心が周辺国と比べ高い。労働組合に関する法律は以下の通りである。
労働組合に関する法律2000年第21号(Law No. 21 of 2000 on Trade Union/Labor Union)
適切に登録された労働組合は以下の権利を有する。a)労働協約交渉の権利、b)労働争議で労働者を代表する権利、c)労働関係機関で労働者を代表する権利、d)労働者の福祉改善のための団体の設立や活動の権利、e)現在施行されている国の法や規則に反しない範囲で労働・雇用関連活動をする権利(労働組合法25条)。
産業関係紛争解決に関する法律2004年第2号(Law No. 2 of 2004 on Industrial Relations Disputes Settlement)
会社と労働者又は労働組合は、両者間での労使関係の紛争解決につき、双方の利益となるよう努力しなければならないが、協議によっても合意に達しない場合、法律で決定し指定された労使関係紛争解決の手続きを通じて解決しなければならない(労働法136条1項、2項)。
産業関係紛争解決法は、会社と労働組合を含む労働者側との間での、権利、利益(雇用契約の変更等)、若しくは雇用関係の終了に関する問題、又は労働組合間の紛争そのほかに関して適用される法律であり、二者間交渉や仲裁などについての紛争解決手続が示されている。紛争解決の方法により、斡旋、調停、仲裁、産業関係紛争解決機関、最高裁判所のいずれの関与となるかが異なるため、注意が必要である。
-
社会保障
社会保障運営機関(BPJS)法2011年第24号(Law No. 24 of 2011 Social Security Organizing Agencies)(改正オムニバス法によって一部改正)
インドネシアはJaminan Sosial Tenaga Karja(JAMSOSTEK)と呼ばれる社会保障制度を有していたが、2011年の新法により2014年から社会保障組織機関による新たな制度運用(Badan Penyelenggara Jaminan Sosial(BPJS))に切り替えられている7。新法令下では、インドネシア労働者のみならず、6カ月を超えてインドネシアで就労をする外国人労働者についても、老齢保障(Old Age Security Program)、年金保障(Pension Security Program)、医療保険8(Health Care Security)、労災補償(Occupational Accident Security Program)、死亡保障(Death Security Program)への加入が義務付けられている。労働者には労災補償を除いた、会社には死亡保険を除いた、各保障・保険への指定割合での資金の拠出が求められる。
上記の保障に加え、改正オムニバス法において、失業保障(Jaminan kehilangan pekerjaan)が追加された。労働者は適切な生活水準を維持するため失業保険を提供され、現金給付、就職支援、職業訓練がされる。失業保障は最大で給料の6カ月分とされる(改正オムニバス法82条)。
-
労働者の安全保障、社会福祉関係等
労働安全衛生に関する法律1970年第1号(Law No. 1 of 1970 on Occupational Safety and Health)
-
外国人労働者
入国管理分野に関する法律2011年第6号(Law No. 6 of 2011 on Immigration)(オムニバス法及び法律2024年63号によって一部改正)
同法は旅券、出入国に関する停止・拒否及び調査権限等につき規定し、入国管理について定める。
外国人労働者利用に関する政府規則2021年第34号(Government Regulation No. 34 of 2021 on the Use of Foreign Workers in Indonesia)
同政府規則は、外国人労働者のための就労許可の利用について規定した同名の大統領規則2018年20号に代わる規則として2021年2月2日付で施行された。従来、大統領規則2018年20号においても定められていた外国人雇用計画書(RPTKA)についての労働省の承認不要となる範囲が拡大されていることが注目される。
外国人が就労可能な役職に関する労働移住大臣決定2019年第228号(Minister of Manpower and Transmigration Decision No. 228 of 2019 on the Positions that Expatriates are Permitted to Work)
本決定は、外国人が就労可能な役職を別表に記載している。したがって、今後インドネシアで就労する外国人は原則として同表から役職を選択することになる。ただし、同決定は、雇用主が必要とする役職が同表に記載されていない場合にも個別申請によって労働省から外国人駐在員の雇用許可を取得することを認める。なお、外国人駐在員のための役職とその要件は少なくとも2年ごとに、又は必要に応じていつでも見直される旨も規定されている。
就業規則の作成義務およびその内容
就業規則の作成義務
-
作成義務
会社は10名以上の労働者を雇用するとき、就業規則9を作成し、労働大臣又は大臣に代わる者の承認を受けなければならない(労働法108条1項)。但し、外国資本の会社の場合、就業規則の作成は人数に関係なく必須となる。なお、会社が労働協約を有している場合には、就業規則の作成義務はない(同2項)。
-
注意すべき点
就業規則については、有効期限が最長2年であり見直しが必要となる点、作成にあたっては労働者代表者からのヒアリング及び推薦を要する点、インドネシア語での作成が義務付けられる点、政府当局の承認を得なければ有効とならない点、会社に、周知・説明義務が課される点、等に注意が必要である。
又、他の法律、協定、規則の適用における優先順位との関係では、拘束力のある順に、①労働法を含む労働保護法規、②労働協約、③雇用契約、④就業規則とされている。
就業規則の内容
-
必要記載事項
下記については、労働法上記載が必須となる(111条1項)。
- ①会社の権利及び義務
- ②労働者の権利及び義務
- ③就労環境・条件
- ④労働者の行動の規律及び規範
- ⑤就業規則の有効期限(最長2年)
-
作成手続等
会社の就業規則の作成にあたっては、労働者若しくは労働者により選出された代表者、又は労働組合がある場合には労働組合の代表者から内容についての意見聴取をし、推薦を受けなければならない(労働法110条1項から3項)。
その後、大臣等政府当局10へ就業規則を提出し、審査を受け、提出から30営業日以内に修正等の指示又は要請がなければ就業規則が有効となる(労働法112条2項)。就業規則を受領した当局は6営業日以内に、就業規則の検討を行わなければならない(労働大臣規則2014年第28号8条5項)。
修正等の指示又は要請があるときには書面で通知され、会社は受領から14営業日以内に指示に従った修正等を行ったうえ就業規則を労働大臣又はこれに代わり指定される者へ再提出しなければならない(労働法112条3項、同4項)。
就業規則の内容について、規定した規則はない。懲戒等各警告書の対象となる事由や、従業員の義務としての秘密保持及び競業の禁止、賃金・有給休暇・賞与等の労働条件に関する事項等、会社の必要に応じて定めることとなる。
周知義務
作成又は変更された就業規則について、会社は従業員に対し、周知し、説明する義務がある(労働法114条)。周知は、就業規則の掲示、配布、説明会の開催等によって実務上なされる。
変更
有効期限内に就業規則を変更するときには、作成時と同様に会社は労働者の代表組織と合意をしなければならず、更に労働大臣又はこれに代わり指定される者の承認によって法的効果が認められる(労働法113条)。このため、労働者に対する一方的不利益がなされないよう変更につき配慮される仕組みとなっている。
変更点につき、会社は労働者に対して周知及び説明を行わなければならない(労働法114条)。
賃金(賞与・退職金・残業代)などの法制の概要
賃金の定義
-
賃金
賃金は、①基本給及び固定手当から成る固定給、②変動給及び③残業代から構成される。①の基本給及び固定給については、賃金が基本給と固定給によって構成される場合、基本給は基本給と固定給の合計額の75%以上でなければならない(労働法94条)との規制が存在しており、注意が必要である。
-
賃金体系
会社は勤続年数、能力を考慮した賃金体系を設け、当局に提出しなければならない(賃金に関する政府規則 2021 年第36号及び賃金構造と体系に関する労働大臣規則2017年第1号)。賃金体系は、就業規則又は労働協約とともに提出されるものとされ、違反した会社は警告書による通知を受け、事業の活動制限を受ける可能性がある。会社は、社員の職務内容、責任、難易度等を考慮して、賃金体系及び給与水準を策定するよう努めなければならないとされている(労働大臣規則2017年第1号第2条1項及び92条1項における憲法裁決定第168/2023)。
-
残業手当
1日8時間(週5日勤務の場合)又は7時間(週6日勤務の場合)までで、かつ、1週間計40時間までが通常の就業時間として認められる(労働法77条2項)。この就業時間を超える労働については原則として、労働者の同意とともに、1日4時間かつ累計で週18時間を上限として認められる(労働法78条1項b)。雇用している従業員が残業をすることを求める会社は残業代を支払う義務がある。一方、政府規則2021年35号は経営者、管理者等一定の職務に当たる者については対象から除外できる旨規定している(政府規則2021年35号27条)。しかし、上記政府規則は対象者を正確に定めているものではないため、当局に照会するのが好ましい。
残業代は月給を173で除した商(月給÷173)を1時間当たりの「基礎賃金」として被乗数とし、以下のように計算される。
このほかに、一日あたりの残業時間が3時間以上となる場合には、最低1,400キロカロリー以上の食事と飲料を提供しなければならない(政府規則 2021年35号29条第1項c)。
支払方法等
-
支払方法
通貨払い(ルピア)で、対象期間および賃金支払日に全額支払われなければならない(政府規則 2021年第36号54条)。
-
支払時期
3カ月以上連続して、会社が所定の時期に支払いを行わない場合、労働者は、労使関係紛争の解決を求める機関に対して雇用契約の終了を正式に要請する可能性がある(労働法154A条1項g (3))。
最低賃金(Minimum Wages)
労働者が人道的な観点から見て人並みに暮らせるようにするために、政府は労働者を保護する賃金施策を設けることとされており、その中で最低賃金も定める(労働法88条2項、同3項a)。最低賃金を下回る額での賃金の支払いは労働法上禁止される(労働法88E条2項)。
具体的最低賃金についてインドネシアでは、例年11月末頃までに各州・県・市が翌年の最低賃金を決定し、公表する。したがって、会社の地域に適用される最低賃金に関する確認が必要となる11。公表されている最低賃金は毎年見直され、翌年1月1日に発効に至る。
最低賃金は、州別最低賃金(UMP)及び県・市別最低賃金(UMK)で構成される(労働法88C条1項、2項12)。最低賃金の計算式は、経済成長率、インフレ率および一定の指標を考慮する(労働法88D条2項13)。
上記の最低賃金に関する規制の違反に対しては、1~4年間の有期懲役若しくは1億~4億ルピアの罰金又はその両方が科せられる(労働法185条)。
退職金
退職金には、退職手当(Severance Pay/ Uang Pesangon)、勤続慰労金(Tenure Reward / Uang Penghargaan Masa Kerja)、権利損失補償金(Compensation of Rights/ Uang penggantian hak yang seharusnya diterima)、及び解雇金(Detachment Money / Uang Pisah)がある。退職金の計算方法は賃金に基づくもので、労働法に定められている(算定の基礎となる「賃金」とは、ここでは基本給及び固定手当を合わせたもの(固定給)を指す)。具体的な各手当の支払倍率等については、更に解雇原因ごとに労働法上の定めが置かれているため、雇用者は労働者の退職時に都度法令の確認が必要となる。
-
退職手当(Severance Pay/ Uang Pesangon)
会社は労働者に対し少なくとも、以下の表に従って退職手当の支払いをしなければならない(労働法156条2項)。
-
勤続慰労金(Tenure Award/ Uang Penghargaan Masa Kerja)
会社による勤続慰労金の支払額は、以下の表の通りである(労働法156条3項)。勤続慰労金についても労働者の勤続年数に応じた支払いが必要となる。
-
権利損失補償金(Compensation of Rights / Uang penggantian hak yang seharusnya diterima)
権利損失補償金とは、以下を含むものである(労働法156条4項)。
・有効かつ未取得の年次有給休暇
・最初に雇用された地域へ労働者及びその家族を戻すための帰省費用(支払がなされていない場合)
・労働協約、就業規則、又は雇用契約で定められたその他の保障
-
解雇金等(Detachment Money / Uang Pisah)
労働者による希望退職及び緊急違反に基づく労働者の解雇等の際、会社は解雇金を支払わなければならない(GR35/2021第49-54条)。支給額及び具体的条件については、あらかじめ労働協約、就業規則、又は個別雇用契約で定めておくため、実質的に労働者側の合意を要する形となっている。このほか、労働協約等により送別金等の名目で懲戒解雇や無断欠勤等の場合にも一定の手当てを任意で設ける会社もある。
賞与・宗教祭日手当等
-
賞与・ボーナス
インドネシアの労働法上、賞与やボーナスに関する規定は存在していない。このため、会社は労働協約や雇用契約等で規定を設けていない限り、支払いの義務を負わない。
-
宗教祭日手当
賞与の代わりに、インドネシアでは宗教祭日手当(Tunjangan Hari Raya(THR))なるものが存在している。
会社は、1カ月以上勤務した労働者に対して宗教祭日手当を現金で支払わなければならない(労働大臣規則2016 年第6号)。
イスラム教徒の多さから実務上イスラム教断食明け大祭の前に支払われることが多いが、本来は各宗教の祭日の7日前に支払うものとされている。
一般的な休日等
-
祝日
祝日等の勤務については、原則として休日出勤と同じ賃金による支払いとなる。
2025年の祝日は以下の通りとなっている。
-
長期休暇
インドネシアでは、会社が長期休暇の制度を設ける必要がある。長期休暇の制度を設ける場合には、関連する雇用契約、会社の就業規則、または労働協約のいずれかで定められ、明記される(労働法79条4・5項及び憲法裁決定168/2023)。
-
祈祷休暇
信仰上義務付けられた祈祷を行う労働者については、会社が祈祷のための十分な機会を保障しなければならない(労働法80条)。又、労働者が宗教上の祈祷実施のために勤務できない場合について、会社は有給休暇扱いとし、賃金を支払わなければならない(労働法93条2項e)。
-
慶弔休暇
会社は、労働者が以下の理由から勤務しない場合、有給での休暇として扱わなければならない(労働法93条1項及び4項)。
-
年次有給休暇
12カ月連続勤務後、会社は労働者に対して最低12営業日の年次休暇を与えなければならない(労働法79条3項)。最低日数に応じた年次休暇取得については、労働協約、就業規則又は雇用契約で定められ、明記される(同4項)。上記年次休暇に加えて、会社は雇用契約、就業規則、または労働協約に規定されている長期休暇を提供できる(同5項)。
-
その他傷病休暇等
医師の診断書(インドネシアでは比較的取得し易い)があれば日数に関係なく有給での傷病休暇扱いとなるため、労働法上、下記の割合での固定給の支払いが義務付けられている(労働法93条3項)。会社としては、最低でも1年間は傷病休暇を理由として解雇が認められていない等、日本と異なるため注意が必要である。
なお、労働者が選挙で投票するために休む場合は、有給の休日扱いとなるため、勤務を命じる場合には休日手当が必要となる。
普通解雇、懲戒解雇、整理解雇のそれぞれの方法と留意点
雇用関係の終了について
-
概説
雇用関係の終了に関して、インドネシアでは労働者に対し極めて有利に設計されている。例えば、雇用関係を終了できる場合及びできない場合が厳密に示されている。会社はその意思で自由に労働者との雇用関係を終了することができない。又、産業関係紛争解決機関(産業関係裁判所)の決定を待ってからでなければ、原則として雇用関係は終了されず、仮に懲戒解雇の場合であったとしても退職金の支払いが労働法上義務付けられている。
労働法では、雇用関係の終了が極力なされることのないよう、会社や労働組合、労働者、政府に対する努力義務が課せられている(労働法151条1項)。会社は、やむを得ず雇用関係を終了する場合、その目的と理由を労働者および/または労働組合に通知しなければならない(同2項)。上記通知がなされた上で、労働者が雇用関係の終了を拒否した場合、雇用関係の終了に関する問題の解決は、会社と労働者および/または労働組合との間の二者間交渉を通じて行われなければならない(同151条3項)。ここで合意に達しなければ、雇用関係の終了は、その決定が恒久的な法的効力を有する労使紛争解決機関の決定を得た後でなければ実施できない(同4項及び憲法裁決定168/2023)。労使紛争関係を解決する手続中、会社は当該労働者が受け取るはずだった賃金その他の全額を支払う(労働法157A条1項)。
改正オムニバス法で改正された労働法154A条は以下の解雇事由を定めている。
a. 会社が合併、統合、買収、または分割され、労働者が雇用関係を継続する意思がないか、雇用主が労働者を引き続き雇用する意思がない場合
b. 会社が損失を理由に会社を閉鎖、または閉鎖せずに効率化(efisiensi)を行う場合
c. 会社が2年間継続して損失を被ったために閉鎖される場合
d. 会社が不可抗力により閉鎖した場合
e. 会社が債務の返済を遅延している状態の場合
f. 会社の破産を宣告した場合
g. 労働者が、会社による以下のような行為を理由に、雇用関係終了を求めた場合
労働者に対して、虐待、屈辱、脅迫した
労働者に対して、法律に違反する行為をするよう説得、命令した
会社が、仮にその後、期日通りに賃金を支払ったとしても、3カ月以上連続して規定の期日までに賃金を支払わなかった
労働者に対して約束された義務を履行しなかった
労働者に決められた業務以外の業務を命じた
雇用契約に含まれていない、労働者の生命、安全、健康および道徳を危険にさらす業務を行わせた
h. 労使関係紛争解決機関による決定があり、会社が労働者によって提出された申請に関して(g)で言及された行動を犯しておらず、会社が雇用関係を終了することを決定した場合
i. 労働者が以下の条件を満たしたうえで自己都合退職した場合 1. 退職日の30日前までに書面で辞任届を提出する2. 退職が業務と関係づけられていないこと 3.辞任の日まで義務を遂行し続けること
j. 労働者が、正当な証明書を添付した書面による説明なしに5営業日以上連続して欠席し、会社によって2回適切に書面で召喚された場合
k. 労働者が、雇用契約、就業規則、または労働協約の規定に違反し、雇用契約、就業規則、または労働協約に別段の規定がされている場合を除き、それぞれ最大6カ月間有効な第1、第2、および第3の警告書を与えられていること
l. 労働者が犯罪行為を行なったとして当局に勾留された結果、6カ月経過しても業務を行うことができない場合
m. 労働者が労働災害のために長期の病気または障害を経験し、12カ月の制限を超えた後に仕事に復帰できない場合
n. 労働者が定年となった場合
o. 労働者が死亡した場合
労働者および/または労働組合に対する通知を要しない、以下の状況についての説明
- 労働法151A条で定められている以下の場合
a. 労働者が自らの意思により退職する場合
b. 有期雇用契約で定めた期間が満了した場合
c. 雇用契約、就業規則、労働協約で定められた定年に達した場合
d. 労働者が死亡した場合
- 労働法151A条で定められている以下の場合
-
解雇に至るまでの流れ
前述のように、会社は産業関係紛争解決機関の決定を受けた後にのみ解雇を行うことができる(労働法151条4項)。会社側都合による退職となる場合には、以下のような手続きを踏む。
産業関係紛争解決機関の決定によらなくても良い自己都合退職のとき、労働者は退職日より30日以上前に、会社に退職届を提出することが義務付けられている(労働法154A条i (1))。
労働者の自己都合等による退職であったとしても、後に会社都合による退職であった等として争われないようにするために、上記と同様の手続きを踏み産業関係紛争解決機関への登録を行うこともある。
-
留意点
労働法では、下記を理由として労働者を解雇してはならないとされているため、解雇にあたって確認が必要となる(労働法153条1項)。
解雇が制限される場合
a.疾病のため継続して12カ月を超えない間勤務が不可能な場合で、医師の診断書による裏付けがある場合
b.法律、法律上、規定されている国家に対する義務の履行のため、勤務が不可能な場合
c.宗教的義務として祈祷を行う場合
d.結婚する場合
e.女性で、妊娠、出産、流産、又は授乳する場合
f.同じ使用者の労働者と血縁又は婚姻関係を持つ場合
g.労働者が労働組合を結成し若しくは組合員若しくは運営者になる場合、
又は労働者が労働時間外に、または就業時間中に会社の許可を得て、若しくは雇用契約、労働協約、就業規則等の規定に基づいて組合活動を行う場合h.会社が犯した犯罪行為について、権限を有する機関に対して訴えを行った場合
i.信条、宗教、政治的思想、民族、肌の色、社会的階層、性別、身体的状態、又は配偶者の有無による相違を理由とする場合
j.労働災害、職業病等労働者が労働に起因して恒久的な身体的障害を負い、又は疾病に罹患した場合で、医師の診断書によって快復までの期間が確定できないものとされた場合
普通解雇
インドネシアにおいては、労働者の能力不足等を理由とする、日本で可能な、いわゆる普通解雇に当たるものは認められていない。このため、会社においては安易な雇い入れにより解雇ができない事態とならないよう、労働者雇用を該当するさまざまな労働協約など、いくつかの要素も含め吟味する必要がある。
懲戒解雇
-
警告書
インドネシアでは警告書発行手続が法により定められている。警告書は第1警告書から第3警告書までの三段階に分かれており、会社は予め労働協約、就業規則、雇用契約のいずれかで、各段階の違反事由を定めておく(減給等の記載が可能14)。会社は連続してこれらの警告書を労働者に発し、第3警告書を発出し終えてなおも労働者の違反行為がみられたときに解雇をすることができる(労働法154A条1項k)。なお、次項でも詳しく述べる通り、懲戒解雇の場合であっても産業関係紛争解決機関の許可が必要となる点は日本と異なるため注意を要する。
具体的な警告書手続の流れは次の通りである。まず会社は、各段階に記載された違反行為を確認後、警告書を発し、当該警告書の発令からいずれも6カ月以内に警告書記載違反事由があれば下記の表に従い再度警告書を発する。これを繰り返し、第3警告書発令後も6カ月以内の違反が認められれば懲戒解雇となる。この6カ月は、違反を受けての労働者の再評価の機会を担保するものと考えられている。6カ月以内に同様な違反が認められなかった場合には、警告書の積み上げはリセットされ、次回の違反は1回目の違反行為扱いとなる(参照:労働法154A条1項k)。
警告書の内容については、労働協約等で定める際にも労働組合を含む労働者の合意を得なければならないため、会社が自由に各段階の警告事由を設定できるというわけではない。又、仮に労働者によって同意され該当事由を会社の有利に設定できたとしても最終的な解雇の判断を行う労働省が会社側判断の承認をしないというおそれもあるため、手続きは慎重に行われなければならない。
-
懲戒解雇に至るまでの流れ
第3警告書を発し、なおも違反が認められる場合に会社は懲戒解雇を決定できる。その後、会社は産業関係紛争解決機関による承認を求める必要がある。
-
その他留意点等
懲戒解雇の場合であったとしても、解雇手当が発生する点に注意を要する。
無断欠勤の場合は、会社が二度労働者を呼び出し、書面で無断欠勤により解雇に至る可能性がある旨の注意をしなければならず、それにもかかわらず、5日以上連続で無断欠勤(書面による事情の説明及びそれを裏付ける証拠の提出がある場合を除く)をした場合に労働者を解雇できる。当該欠勤は、当該労働者の雇用継続の資格を剥奪する可能性があるため、起業家はまた、当該労働者を書面で2回適切に召喚していなければならない。(労働法154A条1項j)。
整理解雇
会社側による整理解雇は、労働法では以下の場合に限定されている(労働法154A条1項k)。経営困難により会社が従業員を一時的に解雇する場合(いわゆるレイオフ)には、固定給(基本給及び固定手当)の全額支給が必要とされている(労働移住大臣回状 1998年第5号)。
- 整理解雇の原因
- a.会社が損失を理由に閉鎖または閉鎖しない場合で効率化を行う場合(労働法154A条1項b)
b.2年間継続して損失を被ったことによる会社の閉鎖(同項c)
c.不可抗力による会社の閉鎖(同項d)
d.会社が債務の返済を履行できない状態の場合(同項e)
e.会社の破産(同項f)
解雇手当
退職金については、「4 賃金(賞与・退職金・残業代)などの法制の概要」を参照のこと。雇用関係の終了の事由原因によって退職金各項目の支払い額が細分化されているために、雇用関係の終了の際の法令の確認が必須となる。
外国人ビザの種類および取得要件
概説
外国人の雇用については、2015年に4カ月程度で相次いで就労許可の取得についての扱いを翻す大臣規則が出るなどその朝令暮改的な運用により実務上混乱が生じることも少なくない。このため、会社及び労働者は、ビザや就労許可取得の手続きについて、改正の動向を注視する必要がある。
この点、2021年4月1日に、外国人労働者利用に関する政府規則2021 年第34号が施行された。従前、外国人労働者雇用に関して施行されていた外国人労働者利用に関する大統領規則 2018年第20号に代わるものであり、同規則は廃止された。
同政府規則は、外国人労働者のための就労許可の利用について規定した外国人労働者利用に関する大統領規則2018年20号に代わる規則として2021年4月1日付で施行された。従来、大統領規則2018年20号においても定められていた外国人雇用計画書(RPTKA)についての労働省の承認不要となる範囲が拡大されていることが注目される。
政府規則2021年第34号に従い、外国人労働者が取得しなければならない暫定居住許可(ITAS)及び限定滞在ビザ(VITAS)の手続きは一本化されている。VITASはITASと同時にオンラインで申請することができる(新しい習慣の適応におけるビザと滞在許可に関する法務人権省規則2021年34号5条3項、6条3項)。ITASは、外国人が入国後に居住する各地域の移民局において申請を行う必要がある(外国人のビザおよび滞在許可の発行に関する法務人権大臣規則2023年22号第106条4項)。同局で一定の審査、手続後にパスポートに移民局のスタンプが押され、ITASが発行される。
なお、2023年末から2024年にかけて以下に代表される法令の改正・施行等が行われており、本資料ではこの点も踏まえて以下説明する。
・移民に関する法律2011年第6号の第三次改正(法律2024年第63号による)
・外国人のビザおよび滞在許可の発行に関する法務人権大臣規則2023年22号(法務人権大臣規則2024年11号による一部改正も含む。)
・ビザの分類に関する法務人権大臣令2023年M.HH-02.GR.01.04号
出入国・滞在に関するビザ各種
ここでは就労やビジネス目的でインドネシアに入国する際、主に利用されるビザを紹介する。インドネシアでの就労にあたっては必ず下記就労ビザを取得しなければならない。又、出張の場合であっても一定の場合、すなわち①工場での業務指示、②技術指導、③機械修繕保守等については、就労ビザ及び就労許可の取得が必要となるため注意を要する。
近年、政府による工業団地やジャカルタ市内での入国管理の強化がされてきており、滞在者のみならず出張者についてもパスポートや滞在許可証ないし適切なビザの取得が求められるため、会社においては適宜在東京インドネシア大使館の情報を確認することが推奨される。
なお、上記のとおり、政府規則2021年第34号により、外国人労働者の就労および滞在許可申請手続きは簡素化が図られている。ただし、その手続きの詳細は、今後、労働省及び法務人権省各規則により定められる点に注意する必要がある。以下では、現在有効な規定を記載する15。
-
就労ビザ(E23、E24、E25等)
インドネシアでの就労を目的とするビザである。有効期間は最長1年16となっており、滞在期間によって、必要書類が異なる。就労ビザは、主に以下の4つに分類され、さらにその後にインデックスが振られている。
一般の就労:E23B~E23W
デジタル分野での就労:E24A~E24F
嘱託や役員としての就労:E25A~E25F
経済特区(Special Economic Zone)での就労:E23A手続きの流れは周辺諸国と比較するとやや複雑で、外国人雇用計画書(RPTKA)、ビザ発給推薦状(TA-01)、限定滞在ビザ(Visa Tinggal Terbatas(VTT))、一時滞在許可(ITAS)等の手続きを、指定される一定期間内に経なければならない。提出書類も変更される可能性があることがあるため、適宜政府当局に問い合わせをするのが望ましい。
-
マルチ・ビジットビザ(D2、D17)
本ビザにより就労をすることは許されていない。有効期間(60日、180日、1年、2年、5年間のいずれか)内に何度でもインドネシアを訪問できる。1回当たりの訪問は最長60日(延長不可)となる。訪問が60日を超える場合は再入国のために一度出国しなければならない。
- D2:ビジネス、ミーティングへの出席、契約の締結
- D17:インドネシア子会社での監査、生産品質管理、検査の実施
-
ワンウェイ・ビジットビザ(C2、C17、C19、C20等)
就労目的を除く、ビジネス目的用ビザである。
- C2:ビジネス、ミーティングへの出席、契約の締結
- C17:インドネシア子会社での監査、生産品質管理、検査の実施
- C19:販売済み製品に対するアフターサービス等
- C20:機械の設置、修理
-
到着ビザ(B2 /VOA)
このビザは、事前にオンラインで申請するか、指定されたインドネシアの港または空港に到着したときに、日本を含む特定の国からの訪問者に対して発行される。このビザの有効期間は30日以内だが、最大60日間まで延長することができる。このビザの取得により、商談等のビジネス目的で訪問することが可能となる。
就労許可
外国人労働者は、一定の役職及び期間の制約のもとでのみ、インドネシアにおける就労を認められている(労働法42条4項、5項)。業界やポジションによっては、異なる規制等が設けられていることもあるため確認を要する。有効期間についても同様で、業界により異なるが、一般的にマネージャー職以上であれば12カ月の就労許可が認められる。
会社は、外国人を雇用する場合に、外国人雇用計画書(RPTKA)を労働省に提出して承認を得るとともに、外国人労働者利用補償基金(DKP-TKA)の支払をする必要がある(参照:労働法47条1項、政府規則 2021年第34号、労働大臣規則 2021年第8号)。以前は外国人雇用計画書(RPTKA)の提出義務を免除されるのは在外公館職員のみであったが、改正オムニバス法により、①会社の株式を有する取締役ないし理事、②在外公館職員、③緊急事態、職業訓練、一定のスタートアップ企業、業務訪問等の理由で雇用主が必要とする外国人労働者に拡大された。会社は上記承認を得た上で、通知書(Notifikasi)を申請する。通知書(Notifikasi)を取得し、外国人労働者利用補償基金(DKP-TKA)の支払証明書を提出すると、入国管理局からE-mailで雇用主に一時滞在ビザ取得手数料が示される。これを納付すると、審査後、電子査証(e-visa)が発行される17。労働者は電子査証が発行されてから90日以内にインドネシアに入国し、入国後に居住する各地域の移民局において、一時滞在許可(ITAS)の取得手続きを行う。
同通知の申請は、労働省ウェブサイトから行う。上記の手続きには下記のように雇用契約書のコピー等様々な資料の提出が必要となる(政府規則2021年第34号、労働大臣規則 2021年第8号)18。
- 外国人動労者(Tenaga Kerja Asing(TKA))を雇用する会社の企業識別番号及び/またはビジネスライセンス
- 会社の設立証書及び変更証書
- 会社の労働報告書(Wagib Lapor Ketenagakerjaan)
- 雇用契約書の写し
- 会社の組織図
- Understudy worker(外国人労働者が有する技術および専門性の移転のためにアシスタントとして任命されたインドネシア人労働者)を指名する宣誓書
- 外国人労働者の資格に従ってインドネシア人労働者に労働教育と訓練を実施する旨の宣誓書
- 外国人労働者へのインドネシア語教育・研修を促進する旨の宣誓書
- 旅券の写し
- 学業等修了証書、履歴書・経歴書
- 外国人労働者または会社の銀行口座の残高証明
- 外国人労働者の保険証券等の証書等
上記の手続きや必要書類は、今後定められる実施細則により変更される可能性があるため注意が必要である。
注意点
-
ローカル労働者雇用の要請
2015年に一度、外国人労働者一人に対しインドネシア人労働者10人を原則として雇用しなければならない旨の大臣規則が出されたが、同年内に削除されるなどローカル雇用義務の内容は、未だ確定していない部分が多い(労働大臣規則2015年第16号、労働大臣規則2015年第35号)。インドネシアでの外国人労働者受け入れが、インドネシア国民への技術・専門性移行を前提とすることから、外国人労働者1人に対し、インドネシア人労働者1人の雇用が最低限求められるものと考えられるが、具体的人数の目安については、現地法人の設立形態等により異なり、また、労働省の裁量によるところもあるため、外国人雇用計画書(RPTKA)申請の際に個別に政府当局に問い合わせをすることが推奨される。
-
外国人労働者の業務制限
外国人労働者は人事業務や一定の業務の担当となることが禁じられる(労働法42条5項)。また、一定の職務に就く場合を覗いて、異なる使用者に雇用されることは禁止されている(労働大臣規則 2021年第8号)。
-
その他
外国人労働者については、インドネシアにおいて6カ月超の就労をする者に社会保障への加入が義務付けられることに加え、納税者登録番号(Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP))の取得も義務付けられる(所得税に関する1983年法律第7号(オムニバス法によって改正)。