市場の動向やこれまでの常識が目まぐるしく変化する現代、ビジネスでは新たなニーズへの対応や新規事業開発の重要性が高まっている。そのような時代に、イノベーションを生み出す最強人材を養成するキーワードとして《哲学的思考力》を重要視しているという西田氏にお話を伺った。
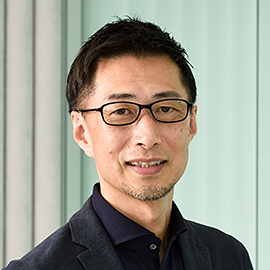
株式会社ブレインパッド 常務執行役員CHRO/人事ユニット統括ディレクター
西田 政之 氏
1987年に金融分野からキャリアをスタート。米国社費留学を経て、内外の投資会社でファンドマネージャー、金融法人営業などを経験。2004年に人事・経営分野へキャリア転換し、人事コンサルティング会社マーサーで取締役COOなどを歴任。その後、ライフネット生命保険取締役副社長兼CHRO、カインズ執行役員CHROなどを経て、23年7月より現職。
日本のデジタル力はなぜ低迷しているのか
VUCAの時代といわれて久しいですが、特に今はIT活用が差別化の源泉となる時代です。にもかかわらず、日本のデジタルスキルは20年も前から低迷し続け、IMD※1のデジタル競争力ランキングでは世界64カ国中35位(2023年)と過去最低順位に凋落。人材のデジタルスキルやデータ活用においては、ほぼ世界最下位レベルです。日米のIT投資額の比較でも大きな差が開いており、1994年には1.4倍の差でしたが、2016年にはその差が4倍に開いています※2。
この背景には、過去のIT導入における日本の経営のリーダーシップ不足があるといえます。海外の企業ではイノベーション実現のために、IT投資が積極的になされてきたのに対し、日本ではコスト削減や効率化を優先したIT活用にとどまっていました。また現場の抵抗を避けて、現行プロセスに合わせた過剰なアドオンの開発を重ねた結果、技術的負債にもつながっているのです。
これからの変化の時代には、IT活用のビジョンの提示、組織横断的な事業変革、イノベーション実現のための投資をさらに強化する必要があり、それには経営者による強烈なリーダーシップが不可欠です。
あらゆる仕事に必要なサイエンスとアートの力
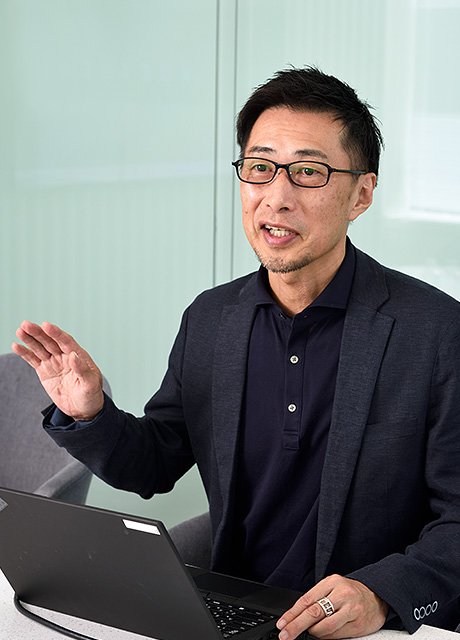
こうした強烈なリーダーシップを追求する上で鍵となるのが、《サイエンス》と《アート》です。現代はあらゆる仕事において、サイエンスとアートの力が必要だと思います。例えば、データ分析から見えてくるファクトをベースに、現場で起こっていることを把握するのがサイエンスの力。その現状に沿ってディレクションやプランニング、マーケティングをするときにはアートの力が必要です。日本の経営者はサイエンスに弱く、欧米の経営者は逆にサイエンスに強い。今後は日本でもサイエンスのセンスを兼ね備えた経営者が必要になるでしょう。
2023年7月に私がCHROに就任したブレインパッドは、日本最大級のデータサイエンティスト集団を擁するデータ分析のプロフェッショナルファームです。理系の博士号所持者など、サイエンスに強い人材が揃っています。「BrainPad HR Synapse Initiative」と名付けた新人事戦略では、彼らが持つ「データ分析力」というサイエンスの力をベースに、「哲学的思考力」と「ビジネスの実践力」を掛け合わせることでイノベーションを生み出す最強人材の育成・輩出を目指します。中でも注力しているのが、「本業を極めたければ異分野を学べ」を合言葉にアート、特に哲学を中心としたリベラルアーツを学ぶことです。
自分の道は自分で考える1億総哲学者の時代

哲学とは、物事の本質を徹底的に考えて解き明かす営みです。個の課題を突き詰めると、必ず哲学に行き着きます。かつては一部の思考力の高い人や哲学者が物事の在り方を考え、人々はそのフォロワーとしてついていけばよい時代もありました。しかし、現代は追従すべき「誰か」がいない状態で、誰もが自分の道を自分で考え、切り開き、決断していくしかない。つまり、一人ひとりが哲学者になるべき「1億総哲学者の時代」を迎えています。
今を生きていくための《哲学的思考》を身に付けるには、私は次の5つが大事だと思っています。1つ目が、情報を盲目的に受け入れず、論理的に分析する「批判的思考」。2つ目が、具体的な状況から一般的な原則や概念を抽出する「抽象的思考」。3つ目が、情報を系統的に整理し一貫性のある結論を導き出す「論理的思考」。4つ目が、事象の背後にある本質を探る「深い洞察」。5つ目が、事象を異なる視点から考察する「多面的な視点」です。
これらを習得するには、問いを立てて考える技術と独学を深める手法を学ぶことが重要です。こうした力を開発するため、「BrainPad Liberal Arts Core」として希望者の誰もが、創発を促す他分野を学べるよう研修体系を整えました。24年はまず環境整備の1年ですが、今後の3年間で個や組織が変化していくのが楽しみです。
歴史や哲学の中には、古の天才たちが考え抜いて出した答えがあります。彼らの思考をベースに自己探索する機会を増やし、哲学的思考を深める。それこそが、予測困難なこの時代に真の意味で自分の頭で考え抜ける人材の養成につながり、ひいては持続可能な未来づくりへの貢献になるのだと信じています。
※1 スイスの国際経営開発研究所
※2 総務省「平成30年版 情報通信白書」
※文中の内容・肩書等はすべて掲載当時のものです。
THEME
注目のテーマ
CONTACT US
お問い合わせ
こちらのフォームからお問い合わせいただけます