人事領域のプロフェッショナル人材として、日本企業や外資系企業を渡り歩いてきたアステラス製薬 専務担当役員 人事・コンプライアンス担当(Chief People Officer and Chief Ethics & Compliance Officer – CPO & CECO)の杉田勝好氏。杉田氏は「人材版伊藤レポート2.0」の検討会メンバ−でもある。グローバル展開の有無に関わらず、日本企業の人事が実践すべきことを伺った。
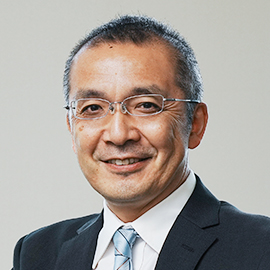
アステラス製薬株式会社 専務担当役員
人事・コンプライアンス担当(CPO・CECO)
杉田 勝好 氏
1991年旭化成に入社。ジョンソン・エンド・ジョンソンを経て、2008年から日本ヒルティ人事本部長、2012年からアストラゼネカ執行役員 人事総務本部長、2016年から日本マイクロソフト執行役員 常務 人事本部長。2021年5月よりアステラス製薬人事部門長を経て、2022年10月1日付で専務担当役員 人事・コンプライアンス担当(Chief People Officer and Chief Ethics & Compliance Officer – CPO & CECO)に就任。
アステラス製薬株式会社
医薬品の製造・販売および輸出入。
1923年創業。従業員数14,522名(2022年3月31日現在、連結ベース)。
日本企業を前提とした議論に陥らないよう注意
――「人材版伊藤レポート2.0」の検討会へはどのようなスタンスで参加されましたか。また、参加して感じたことを教えてください。
個人的に「日本企業はまだまだやれるにもかかわらず、そのポテンシャルを発揮できておらず、このままでは企業も人材も伸びない」という危機感がありました。ですから、「人材版伊藤レポート2.0」の検討会は、日本企業の将来に向けて何か少しでも貢献できることがあれば、というスタンスで参加しました。
私はこれまで日本、アメリカ、ヨーロッパの複数企業で人事領域を見てきたため、その辺りの知見を求められていたと思います。検討会では一橋大学の伊藤邦雄先生から、日本企業の特徴に関する投げかけがありました。日本の中だけで話をしていると、いろいろなことが「日本はこういうもの」といった前提で話が進んでしまいがちです。例えば、「日本人はエンゲージメントが高い」「日本人は勤勉」といわれますが、本当にそうなのか――。こうした日本企業に対する思い込みを前提にした議論にならないように心がけました。
――具体的にどういった点に気つけるべきでしょうか。
日本は世界と比べても教育を受けている人の比率は高いです。しかし、大学を卒業したあと成長できる仕組みがあるかというと、そうではありません。このままではリーダーが育たず、結果、リーダー層に日本人がいない日本企業が増えるでしょう。こうした議論もなされていない上、それでいいと考えている日本企業は多いかもしれません。
アメリカのGAFAM(Google、Amazon、Facebook、Apple、Microsoft)などでは、素晴らしい人材がリーダーシップを発揮して、さまざまなビジネスやカルチャーを変革しています。ビジネスを継続させるためには優れたリーダーが欠かせないでしょう。
金融市場からの要請で覚醒する人的資本経営
――リーダーが育つ風土が整っていない日本企業で人的資本経営を推進していくことは難しいのでしょうか。
そのようなことはありません。私は人的資本経営の話をポジティブに捉えています。「人材版伊藤レポート2.0」の検討会には、投資家やアナリストのかたが多く参加されていました。今後は、「ビジネスを拡大させるための採用戦略がどの程度進んでいるか、およびその結果を聞くようになる」とおっしゃっていました。5年ほど前と比べて状況は大きく変わっており、隔世の感がありました。金融市場からの圧力によって、日本企業の人的資本経営は進むのではないでしょうか。
――「投資家への説明責任は人事のトップが担うべきだ」といった意見もあります。どのような点に注意すべきですか。
「このデータが見たいと言われたから出す」という話ではありません。まず、ミッションやパーパスがあり、それに紐づくビジネス戦略、人事戦略があり、それらを裏付けるデータはこれと、説得力のあるストーリーを語れることが重要なのだと思います。
実行力を最大限引き出す社内環境の構築
――アステラス製薬で実践されている人的資本経営の取り組みについて教えてください。
アステラス製薬は中期経営計画である「経営計画2021」において、「戦略目標」「組織健全性目標」「成果目標」という3つの目標を明示しました。中でも、「組織健全性目標」が作られた背景が一つの鍵だと考えています。アステラス製薬が2025年までの持続的かつ大きな成長を実現するために、何が弊害になっているのかを従業員にインタビューしたところ、「組織を健全化させることが重要だ」という結果が出ました。
最終的に生まれた「組織健全性目標」の具体的内容は、「果敢なチャレンジで大きな成果を追求」「人材とリーダーシップの活躍」「One
Astellasで高みを目指す」の3つでした。「組織健全性目標」を一言で表すと、「イノベーション」です。イノベーションを起こし、実行する力を最大限引き出す社内環境を整えようとしています。
――「組織健全性目標」をはじめとした人的資本経営のフレームワークは、誰が構築すべきですか。
アステラス製薬はゼネラリスト志向の強い会社だったのですが、私はその道のスペシャリストが行うべきだと考えています。先日、ファイナンスのプロフェッショナル人材をCFOとして迎えました。改めてスペシャリティは必要だと実感しています。
とはいえ、日本企業では経験を積める機会が減ってきていると思います。一方で、外資系企業を経験してきた人材や、発展途上の海外法人の立て直しを経験した人材が日本企業に転職し、CFOやCHROなどといった各領域のトップに就く人が増えています。より自分で実行してみたかったのだと思います。私も実はその気持ちが強く、「実際にやれる」という点に魅力を感じてアステラス製薬に入社しました。
リーダーの発掘・育成と社内公募が鍵に
――経営層とプロフェッショナル人材によって構築された人的資本経営を現場に浸透させていくために、どのようなことが必要ですか。
「リーダー」が変わらなければ、現場は変わらないと思っています。人間は年齢を重ねると変わりにくくなります。例えば、定年退職まで5年しかなければ、そのまま変わらないことを望んでしまいます。しかし、アステラス製薬のリーダーは、たとえ定年退職の前の日であっても、さらによくしていきたい、と思える人材でなければ困ると伝えています。リーダー自身が会社のカルチャーなのです。
――リーダーの育成のほかに、日本企業がすぐに実践できることはありますか。
社内公募を大きく広げることは、すぐに始められることだと思います。アステラス製薬は「フリーコンペティション」で、空いているポジションの情報をすべてフルオープンにしています。ポジションが空く前から行きたい部署にコンタクトを取り、意思表明を行うこともできます。また、部署ごとに説明会を実施してもらっています。公募の人気がない部署には努力してもらいたいという考えです。
今後はエンゲージメントサーベイの結果もフルオープンにできないかと考えています。現在は他部署の情報までは見られないのですが、サーベイの結果を公開することで、人材が集まらなくて困る部署が出てくるかもしれません。しかし、「この部署で働きたい」と思ってもらえるよう、改善に向かって進んでほしいと思います。
――最後に、日本企業の人事部長や人事関係者の皆さんにメッセージをお願いします。
成功している企業は人や組織、カルチャーを大切にしています。今ほど「人事によるビジネスへの貢献」が求められている時代はないのではないでしょうか。これは大きなチャンスです。今まで思案はしていたけれど実行に移せなかったことがあれば、積極的に仕掛けてほしいと思います。
※文中の内容・肩書等はすべて掲載当時のものです。
THEME
注目のテーマ
CONTACT US
お問い合わせ
こちらのフォームからお問い合わせいただけます