「世界経済フォーラム(WEF)2024」のテーマが「信頼の再構築」であったように、今さまざまな問題を解決するための鍵として、「信頼」が世界的に注目されている。経済学を幅広く研究し、経済における信頼の重要性についてWEFに寄稿もしたIsmaeel Tharwat氏に、信頼と経済の関係や、組織が信頼を築くために必要なことを伺った。
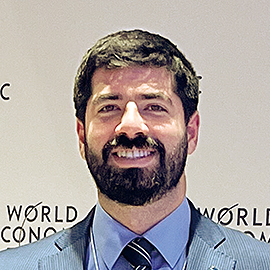
カイロ・アメリカン大学 ビジネススクール 経済学部 助教
Ismaeel Tharwat 氏
パリ・サクレー大学で経済学の博士号を取得。エジプトの地方開発担当副大臣を務め、「アフリカ連合・欧州連合青年協力ハブ」にてアフリカ・ヨーロッパ間の公共福祉向上に貢献した。また、WEFグローバルシェイパーズ・カイロハブのキュレーターも務める。専門は、イノベーションとテクノロジー政策など。
経済格差や不平等がもたらす社会への不信感
世界経済フォーラムが毎年発表している「グローバルリスクレポート」に、度々「社会的結束の喪失」が挙げられていることから、「信頼」の必要性が注目されています。なぜなら、社会的結束とはそれぞれの国や社会がお互いを理解し合い、上手に付き合っていく上で成り立つものであり、「信頼」はその中核となる重要なものだからです。
その背景にあるのは、特に欧米諸国で拡大している不平等という問題です。例えば、アメリカのトップ企業ではフランスやドイツと比べ、役員報酬が2倍の水準にあります。その一方で、アメリカの貧困層から抜け出せる可能性のある人は、フランスやドイツの半数となっています。
こうした経済格差が広がる状況で生じる最大の問題は、人々が社会全体に対して信頼を失っていくことです。自分の国や社会の公正さを信じられなくなれば人々は希望を失い、希望を失えば前に進む活力を失います。私たちが経済的にも社会的にも発展していくためには、人や社会の相互関係が前向きでなければならないのです。
信頼の再構築に求められる4つの要素
では、「信頼」を取り戻すにはどうしたらよいのでしょうか。ミクロ観点で企業に必要な要素は4つあると考えます。
まず1つ目として、優れたリーダーの存在が重要であり、「リーダーシップ」の在り方を見直すことが必要です。企業のリーダーは、従業員が望む価値観を体現しなくてはなりません。そして、人々をひとつにまとめ、結束させることで、文化の壁や先入観、偏見を打ち破ることができるのです。
2つ目は「イノベーション・マインドセット」についてです。社会に生じる問題は、すぐに解決できるものではありません。だからこそ物事をより良く、新しく変えていく考え方が大切で、間違いや欠点と共存しながらも創造性を受け入れ、力を発揮できる人材が必要です。より調和のとれた社会を築くためには、そうした考え方が文化の一部になるべきだと考えます。従業員がイノベーション・マインドセットを体現できれば、経営者はもっと多くのこと――例えば、倫理的・道徳的な課題に取り組み、社会に貢献するための持続可能な経営戦略などを考えられるようになります。そして、企業と政府の間にもより多くの調和が生まれ、企業の目標と国全体の目標を一致させることが可能になります。
3つ目の要素は、「社会的流動性と不平等の解消」です。信頼の喪失を招く経済的不平等に向き合うことが、非常に重要になっています。バックグラウンドに関係なく、皆が自分の力を発揮し、成長できる機会を与えられることが必要です。これは、社会的流動性という観点から政府レベルで取り組むべきものであり、「信頼の再構築」という考えの下、各国間の国際協定が再定義されています。企業も自分たちが持っている偏見を取り払い、その先の平等な世界を模索して、より結束力のある社会を築くために投資するべきです。
そして、最後の4つ目の要素が「アカウンタビリティ(説明責任)」です。近年、24時間365日、人目にさらされるソーシャルメディアの時代において、人々はますます説明責任を果たすことや、自分の失敗や考えに責任を持つことを避けるようになっています。しかし、説明責任は信頼の根幹です。私たちはその重要性を問い直し、説明責任を果たさなくてはなりません。
政府であれ、企業であれ、トップやリーダーは間違いを犯したらそれを認め、反省し、改善するために次の行動を起こすと説明するべきです。もし、すべての組織のあらゆるレベルでそれができれば、信頼を築けるだけでなく、誰もが当事者意識を持ち、社会や企業の中で、自分の将来に責任を持つことができるでしょう。そして、責任を受け入れるからこそ、人々はリスクを恐れず挑戦することができ、失敗から学び、変革を受け入れ、成長していけるのです。
コロナ禍は信頼関係にどう影響したか
信頼関係において、COVID-19は世界中に大きな影響を及ぼしました。例えば欧米のメディアでは、ワクチンの効果に関する報告書をはじめ、透明性が欠如した情報にもかかわらず報道することがありました。多くの国民にとって、これは非常に偏った情報で、信頼できるものではなかったと思います。
また、COVID-19は、企業内での信頼関係にも大きな影響を及ぼしました。人々が対面で接することが難しくなり、多くの企業がリモートワークを導入したことで、働く個人は通勤時間を省けたり、働き方や働く場所に柔軟性を持たせることができたり、環境面においては二酸化炭素排出量の削減にもなったりなど、良いことも多くありました。しかしその半面、誰かと話す、相談するといった職場でのコミュニケーションが大きく制限され、これは企業にとって大きな代償のひとつになりました。なぜなら、職場で実際に会って話し、一緒に時間を過ごすことでお互いの信頼や理解が深まり、それが従業員のメンタルヘルスや士気向上に影響するからです。さらに、職場でのコミュニケーションは会社全体の士気を上げ、技術革新や生産性向上にも良い影響を与えることが分かっています。
企業が今後、誠実さを備えた革新的で生産性の高い、強い組織を目指すためには、従業員一人ひとりのワークライフバランスも考慮した働き方を考えていくことが必要でしょう。そして、従業員や組織にとって、オフィスワークとリモートワークをどのようなバランスで取り入れるのが最適なのかを見極めるには、透明性の高いプロセスで話されなければなりません。
従業員の不信感を払拭するには
信頼が根付いた組織を築く上で、大きな課題となるのが、従業員が「仕事に大きな目的を見いだせない」ということです。また、「自分のしていることが報われない」「仕事が評価されない、その理由が分からない」「上司が自分に協力的でない」など、リーダーとの明確なコミュニケーションがとれないために、従業員の期待が満たされない状態も組織にとっては問題です。
企業は、共通の大きな目的を達成するための集団です。単に仕事をこなすだけでなく、誰もがその目的のために働き、使命を果たしていく中で、自分の人生の意味を見いだしていく場所でなければなりません。こうした問題を踏まえ、信頼関係の強い組織をつくるためには、次の2つのことが必要だと考えます。
1つは、十分なコミュニケーションをとり、どのようなステップで、誰が何をするべきかを明確にすること。「会社が達成しようとしていることは何か」「なぜ会社は自分を必要としているのか」などを明確に伝え、従業員全員が組織の目標や自分の使命を理解することが大切です。
リーダーは時として、現場で起こっている問題から切り離されてしまうことがあります。CEOでもマネジャーでも、従業員をまとめる立場のリーダーは皆、チームや部下の声に意識的に耳を傾け、「優れた聴き手」になろうと努力することが必要です。話を聴く機会をつくり、聴いたことを真に受け止めてください。定期的にコミュニケーションの機会を設けることは、信頼の再構築にとても有効です。
また、このコミュニケーションは、双方向であることが重要です。リーダーが部下に期待することや改善してほしいことを伝えるだけではなく、部下自身が自分で改善できると思うことや意見を聴いて、取り入れ、彼らが組織に貢献できるようにするのです。そうしたコミュニケーションが仲間意識を高め、調和のとれたチームや組織、社会を築いていくのだと考えます。
2つ目のポイントは、信頼の再構築に必要な要素として先程も取り上げた「優れたリーダーシップ」の中核的特質である「真の気遣い」です。組織を率いるリーダーは、チームや部下について常に気に掛け、深い関心を持ち、信じることが必要です。そしてリーダーや上司はそのような思いを持つからこそ、「部下を成長させたい」「個人としても仕事のプロフェッショナルとしても成長できるようサポートしたい」と願うことが、調査や私の経験からも分かっています。
誰でも体験したことがあると思いますが、自分を理解し、認めてくれる優れた上司やリーダーに恵まれたときはやる気が出て、仕事をするのが楽しくなります。逆に、部下のことをきちんと考えてくれない、正当に評価してくれないような上司の下では、仕事へのモチベーションが下がり、会社に行くのさえ嫌になります。つまり、そうした他者を気遣うリーダーの姿勢が、部下の情熱や能力を最大限に引き出し、成長させ、仕事や人生に大きな意義を見いだす助けとなるのです。
リーダーの「誠実さ」が組織の信頼を再構築する
リーダーシップとチームビルディングに重要な原則は、「誠実さ」です。リーダーに求められるのは、失敗を許さない完璧さではなく、部下に敬意と誠実さを持って接し、改善すべきところは求め、常にサポートしていくことです。私は、日本人が大切にしている「改善」という考え方が好きです。うまく機能しないものを切り捨てるのではなく、改めながらより良いものに変えていく姿勢は学ぶべきものだと思うからです。
リーダーは、部下に改善を求めて拒絶されることを恐れないでほしいと思います。自分が正しいと思ったことを、信念に基づいて行動するのであれば、それは理解され、受け入れられると信じてください。
また、リーダー自身も完璧ではなく、完璧であろうとする必要もありません。周囲からの評価や称賛を求める存在でもありません。常に向上していかなくてはならず、すでに無駄のない完成された人間であるように見せるのは、リーダーのあるべき姿ではないのです。もし、チームや部下が「リーダーは自分の評価や称賛のために行動しているのだ」と感じたなら、信頼も組織文化も失われてしまうでしょう。
環境や状況を変えたいと思ったとき、周囲の人を変えるのは容易ではありません。まず、自分自身から変わろうと行動することが大事です。リーダー自身も、部下と同様に改善を繰り返しながら、ベストを尽くす姿を見せてください。そうすることで「誠実さ」が具体化され、インクルーシブ・マインドセット(多様な人々の背景や能力を認め合い、尊重する包括的な考え方)が醸成されれば、組織や社会全体の調和や信頼が再構築されていくはずです。
※文中の内容・肩書等はすべて掲載当時のものです。
THEME
注目のテーマ
CONTACT US
お問い合わせ
こちらのフォームからお問い合わせいただけます